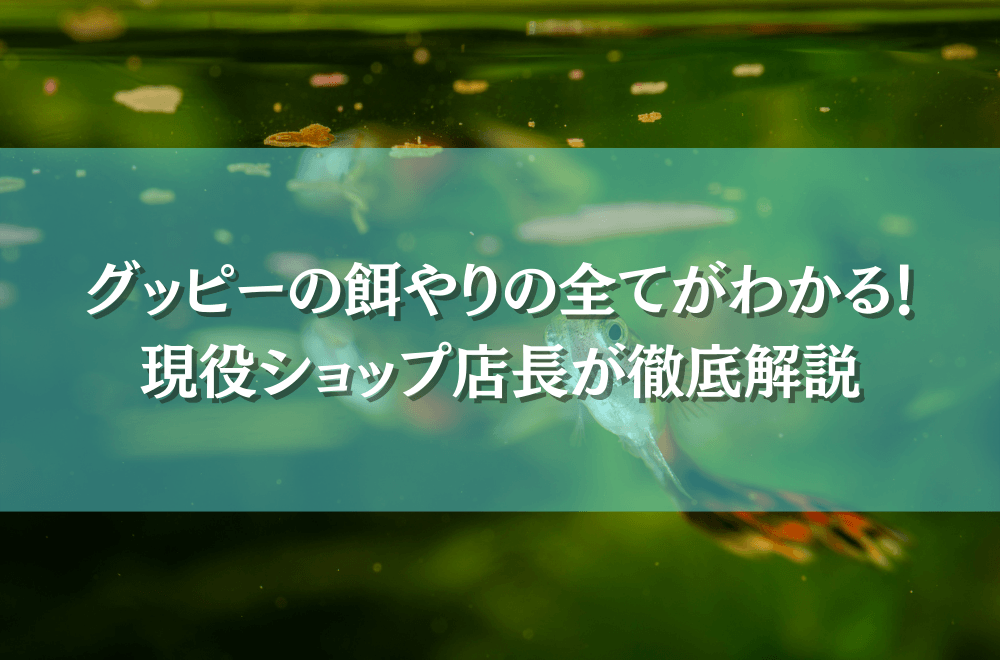
グッピーにおすすめの餌を現役ショップ店長が厳選!餌を食べない時の対処法は?
Share
グッピーの餌の種類と選び方

熱帯魚のなかでも知名度抜群のグッピー。グッピーを飼育する上で大切な餌について種類と選び方について現役のアクアショップ店長が解説していきます。
生き餌
グッピーには生きたブラインシュリンプベビーがよく使われ、グッピーマニアは必ずといっていいほど使う餌です。生きたブラインシュリンプベビーは栄養価や嗜好性が高く、消化吸収も良いので最良の餌と言えます。
ブラインシュリンプは稚魚から親魚まで食べます。他には、イトメです。生きたイトメは嗜好性も栄養価も高く、グッピーを太らせることに適しています。イトメの場合、問題になるのは入手がしにくいことと、生きたまま管理するのが手間なこと、病気の持ち込みリスクがあることです。
冷凍餌
冷凍のブラインシュリンプベビー、コペポーダ、ワムシ、赤虫、ディスカスハンバーグなどもグッピーの餌としては使われることがあります。ブラインシュリンプベビーとコペポーダは種類は違いますが、類似している餌です。
他にもワムシが餌として知られていますが、ワムシはブラインベビーやコペポーダより更に小さな餌です。赤虫はグッピーをはじめ多くの魚に使える万能の餌です。ディスカスハンバーグは、グッピーの体を大きくしたい場合に使うことがあります。
冷凍餌は、冷凍庫さえあれば生き餌のような手間がかからず手軽に使えるのと、自然の餌に近いので栄養価や嗜好性も高いのが特徴です。
ドライフード
ドライフードはグッピーに限らず多くのアクアリストが使う餌で、入手や管理など扱いも簡単なので、手軽に使用できるのが好まれる理由です。各メーカーが特徴のある商品を出していて、選ぶ楽しみもあります。
注意点としては、 開封後の餌の酸化です。ドライフードは開封後から酸化が始まるので、消費期限内だとしても3~6ヶ月以内に使い切るようにしましょう。保管する場合は高温多湿な場所も避けましょう。
袋入りであれば袋内の酸素を抜いた状態で閉め、容器入りであれば蓋をしっかり閉めるよう注意しましょう。
サイアミーズフライングフォックスの飼育法!食べるコケの種類や量は?
グッピーにおすすめの餌TOP5
グッピーにおすすめな餌、TOP5をご紹介します。
NO.5 ニチドウ アルテミア
ブラインシュリンプの乾燥卵の殻だけを除去して、卵黄を取り出した餌です。人工飼料とは違い、より自然に近い餌なので、餌による油膜も出にくい特徴があります。ほぼ自然の餌なので嗜好性や栄養価も高く、人工飼料とは違ったドライフードとしても特色が強い餌です。溶け出し方も違うので、水も汚しにくいのも良い点です。
NO.4 ベンリーパック食品 スーパープレミアム赤虫(ディスカスハンバーグ)
赤虫やディスカスハンバーグです。この赤虫はディスカス向けの高品質なものです。ディスカスハンバーグの場合、慣れの問題で嗜好性が良くない場合があるので、溶かして軟らかくなってから与えてみてください。
ディスカスハンバーグも商品による差があるので、1つ使ってみただけで判断しないで、色々と試すのがいいでしょう。
NO.3 生きたミジンコ
近年ではメダカブームに乗り、生きたミジンコも餌としてよく使われるようになりました。以前に比べると、流通も多くなっていることから、使用するにあたってのハードルが低くなっているためおすすめです。
ミジンコの大きさによってはブラインベビーと同じく、稚魚から親魚まで与えることができます。ミジンコは、自分で増やす楽しみもあるのが魅力です。
NO.2 生きたイトメ
生きたイトメは、昔からグッピー飼育でも用いられてきた活き餌です。個人的には、入手のしにくさや管理の手間、病気の持ち込みリスクなどからほとんど使用しませんが、グッピーの世界では必ず出てくる生き餌です。
グッピー以外の魚でも昔から利用されている餌で、栄養価や嗜好性、消化吸収などを考えると、生き餌であるイトメを与えることにも大きなメリットがあります。
NO.1 生きたブラインシュリンプベビー
生きたブラインシュリンプベビーも、グッピーの定番餌と言えるほど有名です。嗜好性と栄養価に富んでいて、稚魚から親魚まで与えることができ、グッピーにベストな餌と言えるでしょう。
注意点としては、フィルターにブラインシュリンプベビーが吸い込まれてしまうので、対策が必要だということです。上部フィルターや投げ込み式フィルターなどのフィルターを用いた飼育環境には不向きであるため、使用できるのはスポンジフィルターや底面式フィルターなどに限られます。
/
グッピーの餌の与え方(頻度・量)
グッピーには、どのように餌を与えれば良いのかについても解説していきます。
与える頻度(回数)
一般的な愛好家であれば、1日1~3回程度の餌やりが基準となります」。外で働いている人であれば、せいぜいそのくらいの回数になると思います。
1日1回の給餌でもグッピーを飼うことはできますが、立派なグッピーを作りたいとなれば、少量の餌を1日に何回でも与える必要が出てきます。しかし、一度にたくさん与え過ぎると、食べ過ぎたグッピーが死んでしまうこともあるので、そこは様子を見ながら調整するよう気をつけなければいけません。
最悪の場合、お腹が破けてしまうこともあります。
一度に与える量
餌を与える回数のお話でも少し触れましたが、一度に多く食べ過ぎるとグッピーが死んでしまうことがあります。与えれば与えるだけグッピーは食べるため、餌の量は飼育者がコントロールしなければいけません。
目安は、空腹時のグッピーの お腹の膨らみを覚えることです。その状態を覚えれば、グッピーが餌を食べた後のお腹の膨らみがわかるようになります。一度に与える量としては、グッピーのお腹が膨らみ始めたら良しとしましょう。
/
グッピーが餌を食べない原因と対処法
グッピーが餌を食べない場合にはさまざまなケースが考えられます。グッピーが餌を食べない原因と対処法について整理していきましょう。
水温・水質問題
不適切な水質や水温、水質悪化のケースが考えられます。グッピーは酸性に弱い魚なので、たとえば、酸性に強いネオンテトラなどが平気な水質でも、一緒に混泳しているグッピーから死んでいくことがあります。
水換えをしたり、水質調整ができる商品を使って、水質問題をカバーしましょう。水温も、低水温には強いですが高水温には弱いので、水温チェックも怠らないでください。
病気
グッピーのような魚が餌を食べないケースというのは、病気が原因であることも考えられます。代表的な病気にはカラムナリス病があげらあれます。
ただし、水質が酸性に偏って低pHになった場合、グッピーがカラムナリス病のような症状を見せるので、この時にカラムナリス病かどうかの判別が大事です。まずは水質悪化の確認も踏まえて、pHを計りましょう。
ストレス
これは可能性としては1番低いですが、もしもストレスが原因だとしたら、よほど悪い状態と言えます。例えば小さな子供がいて、水槽を四六時中叩いたりしているとか、そのようなことでもない限り、グッピーのような神経質ではない魚が怯えることはほぼありません。
ちなみに、水換え不足で水質が悪化してくると、魚は神経質になりやすくなるので、そういう意味では水質管理と合わせて注意しましょう。
産仔間近
産仔間近なメス個体は、普段とは違う様子を見せることも多いです。例えば、水槽を上下にせわしなく泳ぎ続けたり、逆に、ジッと黙ったままになったりすることもあります。
こうなると意識は食事に向かいにくくなったりもあるので、餌を食べなくなる場合もあります。水槽内の魚の多くが変だったら水質や病気を疑い、特定にメスだけが変だったら産仔間近の可能性も押さえておきましょう。
/
適切な餌やりで、きれいなグッピーを育てよう

グッピーは誰もが育てやすく、繁殖もさせやすい魚です。熱帯魚を飼う楽しさを教えてくれる魚です。しかし、とっても奥深いのもグッピーの世界です。
そんなグッピーを綺麗に育てるために、特に餌と水にはこだわってみてください。そうすれば、きっと綺麗なグッピーを目にすることができますよ。たかが餌、されど餌です。
白点病の原因と治療法をプロが解説!発症初期なら自然治癒する?
ph(ペーハー)は観賞魚飼育にとっても重要!魚種別の最適phと測定方法をプロが伝授!
ゼンスイのアクアグッズ15選!注目商品はクーラーだけじゃない!
メダカ水槽の立ち上げ方!エアレーションの必要性やメンテ方法は?











