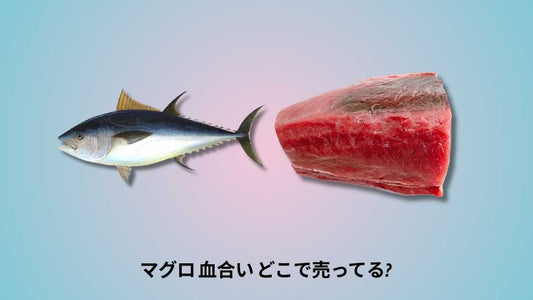カラシンの代表47種類と飼育方法!小型種は初心者にもおすすめ!
Share
アイキャッチ画像出典:写真AC
カラシンってどんな魚?

出典:写真AC
カラシンはカラシン目に分類されている淡水魚の総称です。代表的な種類としては「ネオンテトラ」などのテトラ類がいますが、危険生物として名高い「ピラニア」類も同グループに分類されており、形態や生態は多岐に及んでいます。まずは、カラシン類の特徴などをご紹介します。
カラシンの特徴
カラシンの種類は多いため、形態や大きさ、体色などは様々です。共通する外見的な特徴としては、ほとんどの種類が背ビレと尾ビレの間に「脂ビレ」と呼ばれる小さなひれを持つことと、アゴには鋭い歯が並ぶことが挙げられます。食性は、植物食性が強いものから動物食性のもの、両者を食べる雑食性のものまで種類によりけりです。小型の種類は臆病な性格のものが多いですが、中~大型の種類では気性が荒いものも少なくありません。
カラシン目は魚類の中でも大きなグループ
カラシン目に分類されている魚種は1600種を超え、淡水魚全体の約14%を占める大きなグループです。ちなみに、淡水魚は全体で約12000種に上り、コイ目(約3200種)・ナマズ目(約2800種)・カラシン目の3つのグループで全体の半分以上の割合を占めています。
カラシンの分布
カラシンの分布域はアフリカ大陸と、中央アメリカから南アメリカ大陸にかけてです。カラシンは完全淡水魚で、他の地域には野生種の生息が見られないことから、太古に両大陸が陸続きであった大陸移動説を裏付ける存在として登場することもあります。アフリカには約200種が、残りの約1400種類が中南米に分布しています。
カラシンの寿命
カラシンは種類が多いので寿命も千差万別です。ネオンテトラなどの小型種は3年前後で寿命を迎えるものが多いですが、中~大型の種類では20年以上もの長い寿命を持つものもいます。長い付き合いになる可能性があるので、ご自身が飼育したい種類についてよく調べ、飼い切れなくならないように注意してください。
ポリプテルスセネガルスの飼育や混泳の注意点!古代魚入門におすすめ!
カラシンの代表47種類
前述の通り、カラシンは小型~大型まで非常に多くの種類がいます。ここでは、主なカラシンの種類をご紹介します。
超小型のカラシン
ディープレッドホタルテトラ
| 学名 | Axelrodia riesei |
| 分布 | コロンビア(メタ川) |
| 体長 | 約3cm |
| 価格 | 250~700円 |
*表を埋めた後、50字程度で簡単に特徴を記述してください。表の価格は500~1000円というように幅を持たせてください。見た目の特徴や飼育難易度などを飼いてあげるとよいかと思います。表はコピーして使用してください。(以下、同)
赤色の体色を基調に尾ビレの付け根部分に黒色のスポット模様が入る人気種です。導入時はやや神経質な面を見せますが、水槽の環境に慣れてしまえば以降の飼育は容易です。
テトラオーロ
| 学名 | Hyphessobrycon elachys |
| 分布 | ブラジル(パラグアイ川) |
| 体長 | 約2.5cm |
| 価格 | 120~500円 |
銀色の体色を基調に尾ビレの付け根部分に黒色のスポットが入る種類です。それほど神経質な種類ではないので、飼育は容易です。
ブリタニクティス・イエロー
| 学名 | |
| 分布 | ペルー |
| 体長 | 約3cm |
| 価格 | 850~1300円 |
黄色を帯びる透明感のある体が特徴的な種類です。あまり活発に遊泳する種類ではないので、他種と混泳させる場合は注意してください。
小型のカラシン
ネオンテトラ
| 学名 | Paracheirodon innesi |
| 分布 | ペルー(アマゾン川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 80~180円 |
青色の魚体に赤色のラインが入る、熱帯魚の代表的な種類です。水質にうるさいこともなく飼育しやすいので、アクアリウムの入門種としても最適です。
ブラックネオンテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
| 分布 | ブラジル(パラグアイ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 100~270円 |
名前にネオンテトラと付きますが本種は独立した種類で、ネオンテトラの赤色を黒色にしたような模様が特徴です。ネオンテトラと同様、飼育しやすい種類です。
カージナルテトラ
| 学名 | Paracheirodon axelrodi |
| 分布 | ブラジル、コロンビア |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 100~1000円 |
ネオンテトラに並ぶ熱帯魚の代表種で、赤色のラインが頭部にまで入る鮮やかな色彩が特徴です。飼育も容易なので、アクアリウムの入門種としても最適です。
グリーンネオンテトラ
| 学名 | Paracheirodon simulans |
| 分布 | ブラジル、コロンビア |
| 体長 | 約3.5cm |
| 価格 | 100~300円 |
落ち着いた青色の発色が美しく、体に入る青色のラインが尾ビレの付け根部分にまで伸びることが特徴です。ややデリケートな面を持ちますが、環境に慣れてしまえば落ち着いて飼育できます。
ブラックファントムテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon megalopterus |
| 分布 | ブラジル(パラグアイ川、グァポレ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 100~450円 |
体高がある魚体に大きな背ビレと尻ビレを持つことが特徴的です。体色は灰色を基調に大きな黒色の斑点が入ります。適応力が高いので飼育は容易です。
レッドファントムテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon sweglesi |
| 分布 | コロンビア(オリノコ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 120~350円 |
ブラックファントムテトラの赤色バージョンといった種類ですが、ヒレはそれほどまで伸長しません。赤色の発色を強くしたいのであれば、弱酸性の水質で飼育すると良いです。
ラミーノーズテトラ
| 学名 | Petitella georgiae |
| 分布 | ブラジル(アマゾン川下流) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 80~200円 |
ラミーノーズとは酔っ払いの赤い鼻を意味しており、透明感のある体に頭部が赤色に染まることが特徴です。適応力が高いため飼育自体は容易ですが、頭部の発色を良くしたいのならば弱酸性の軟水で飼育する必要があります。
プリステラ
| 学名 | Pristella maxillaris |
| 分布 | ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約4.5cm |
| 価格 | 100~450円 |
古くから小型カラシンの入門種として知られている種類で、背ビレや尻ビレに入るスポット模様が特徴です。小型カラシンの中では繁殖も容易な部類に入ります。
バルーンプリステラ
| 学名 | Pristella maxillaris var. |
| 分布 | 改良品種 |
| 体長 | 約4.5cm |
| 価格 | 400~800円 |
プリステラの改良品種で魚体が短く、丸みが増している可愛らしい品種です。ヒレなどの特徴は原種のものを受け継いでおり、飼育しやすい品種です。
グローライトテトラ
| 学名 | Hemigrammus erythrozonus |
| 分布 | ガイアナ(エッセクイボ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 60~150円 |
ネオンテトラなどと同様に古くから親しまれてきた種類で、魚体にオレンジ色のラインが入ることが特徴です。適応力が高く飼育しやすい種類です。
ダイヤモンドネオンテトラ
| 学名 | Paracheirodon innesi var. |
| 分布 | 改良品種 |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 120~350円 |
ネオンテトラの改良品種で、青色のラインが消失して頭部が青色に、背中側が銀色に輝くことが特徴です。飼育法はネオンテトラに準拠します。
シルバーチップテトラ
| 学名 | Hasemania nana |
| 分布 | ブラジル(サンフランシスコ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 70~150円 |
黄色を帯びる体色に各ヒレの先端が銀色に染まる種類です。丈夫なので飼育しやすく入門種としても適しています。
レッドチェリーテトラ
| 学名 | |
| 分布 | ブラジル(ジュルエナ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 3600~4600円 |
赤色を帯びる透明感のある魚体に、各ヒレが真っ赤に発色する種類です。ブラジルのジュルエナ川にのみ生息すると言われ、流通量が少ないので高価です。
レモンテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon pulchripinnis |
| 分布 | ブラジル(タパジョス川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 100~150円 |
黄色を帯びる体色に目が赤く染まる種類です。古くから親しまれている種類の1つで、丈夫で飼育しやすく性格も温厚なので混泳にも適しています。
ホワイトフィンロージーテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon sp. |
| 分布 | ペルー、ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 300~800円 |
ピンク色を帯びる魚体に、背ビレと腹ビレ、尻ビレの先端が白色に染まる美しい種類です。丈夫なので飼育は容易です。
ペレズテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon erythrostigma |
| 分布 | ブラジル(ネグロ川) |
| 体長 | 約7cm |
| 価格 | 640~900円 |
体高がある菱形の魚体が特徴的で、やや大型になる種類です。オスは成熟すると背びれが伸長し、フィンスプレッディングは迫力があります。
キティテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon heliacus |
| 分布 | ブラジル(シングー川、タパジョス川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 280~1000円 |
2000年になって初めて輸入された種類で、若魚の頃は白色をしていますが、成長共に黄色を帯びるようになります。尾ビレの付け根に黒色のスポットが入ることも特徴で、飼育は容易です。
コロンビアレッドフィンテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon columbianus |
| 分布 | コロンビア |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 100~850円 |
青色を帯びた金属光沢がある魚体に、尾ビレと尻ビレが赤く染まるコントラストが美しい種類です。やや大きくなりますが、丈夫なので飼育は容易です。
モンクホーシャ
| 学名 | Moenkhausia sanctaefilomenae |
| 分布 | ブラジル、パラグアイ |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 180~300円 |
銀色の体色を基調に、赤く染まる目と尾ビレの付け根に黒色の模様が入ることが特徴です。植物食性が強いので水草との混泳にはあまり向いていません。
コギャルテトラ
| 学名 | Moenkhausia cosmops |
| 分布 | ブラジル(タパジョス川) |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 3000~4000円 |
目が青色で口が赤色になる派手な種類で、アイシャドーと口紅で化粧をしている様を想起させることから名付けられました。流通量が少ない割に人気があるので高値が付きます。
ペンギンテトラ
| 学名 | Thayeria boehlkei |
| 分布 | ペルー、ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 130~300円 |
体に入る黒色のラインが、尾ビレの下側にのみ伸びていく模様が特徴的です。魚体を斜めにしながら泳ぐ様子が可愛らしいポピュラーな種類です。
エンペラーテトラ
| 学名 | Nematobrycon palmeri |
| 分布 | コロンビア(アトラト川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 100~250円 |
目と魚体に入るラインが青色で、オスの尾ビレがフォーク状になることが特徴です。オスは縄張り意識が強くなるので、混泳させる際は水草などを多く入れる必要があります。
ブルーテトラ
| 学名 | Boehlkea fredcochui |
| 分布 | ペルー(アマゾン川) |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 100~250円 |
透明感のある青色の魚体に、背ビレと尾ビレの先端が白色になることが特徴です。小型カラシンの中では気性が荒いので、混泳させる際は注意が必要です。
シグナルテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon ps. |
| 分布 | ペルー(アマゾン川) |
| 体長 | 約3cm |
| 価格 | 600~800円 |
銀灰色の体色を基調に、背ビレに白・黒・橙色の模様が入る特徴があります。水質にうるさいことはありませんが、同種同士では小競り合いすることがあるので注意してください。
コーヒービーンテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon takasei |
| 分布 | ブラジル(アラグアイア川、オイヤポク川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 600~1000円 |
直訳すると「コーヒー豆テトラ」ですが、その名の通り魚体にコーヒー豆に見える大きな黒色の斑点が入ります。神経質ではないので飼育は容易です。
ヒャニュアリーテトラ
| 学名 | Hemigrammus hyanuary |
| 分布 | ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 600~800円 |
「ジャニュアリーテトラ」や「キャッスルテトラ」の名前で販売されていることもある小型カラシンで、銀色の体色を基調に尾ビレの基底部に黒色の斑点が入ります。
ペルーファラゴテトラ
| 学名 | |
| 分布 | ペルー(ファラガ川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 2000~4000円 |
濃紺の体色が美しい種類で、ヒレが赤色になるものと黄色になるものが知られています。流通量が少ないので高値で取引されていますが、今後は増えることが予想されています。
ペルビアンカイザーテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon nigricinctus |
| 分布 | ペルー |
| 体長 | 約6cm |
| 価格 | 2000~3000円 |
金属光沢のある魚体に、黒色の太いラインが入る種類です。デリケートな種類なので水質に注意する必要があります。
ファイアーテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon amandae |
| 分布 | ブラジル(アラグアイア川) |
| 体長 | 約2.5cm |
| 価格 | 60~200円 |
「レッドテトラ」の別名で販売されていることもあり、名前の通り全身が赤色に染まる種類です。奇麗に赤色に発色させるのは意外に難しく、じっくりと飼い込む必要があります。
グリーンファイアーテトラ
| 学名 | Aphyocharax rathbuni |
| 分布 | ブラジル(パラグアイ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 60~400円 |
緑色の体色を基調に、腹部から尾ビレにかけてが赤色に染まる種類です。飼育自体は容易ですが、発色を良くしようと思うのであればしっかりと飼い込む必要があります。
イエローテールテトラ
| 学名 | |
| 分布 | |
| 体長 | |
| 価格 |
コバルトロージーテトラ
| 学名 | Hyphessobrycon sp. |
| 分布 | コロンビア(メタ川) |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 1000~1200円 |
金属光沢を持つ体と、尾ビレの上側にしか入らない赤色の模様が特徴です。それほど神経質ではないので、飼育は容易で混泳相性も良い種類です。
インパイクティスケリー
| 学名 | Inpaichthys kerri |
| 分布 | ブラジル(マディラ川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 150~1300円 |
青色に輝く体に濃紺のラインが入ることが特徴です。飼育自体は容易ですが、やや気性が荒く低めの水温を好む点に注意してください。
レモンラピステトラ
| 学名 | Hyphessobrycon sp. |
| 分布 | ブラジル |
| 体長 | 約5cm |
| 価格 | 2000~3500円 |
黄色を帯びる体色に黒色のラインが入り、各ヒレが黄色に染まります。流通量が少ない珍しい種類として人気です。水質の悪化には弱いので注意してください。
クリスタルレインボーテトラ
| 学名 | Characidae sp. |
| 分布 | ペルー |
| 体長 | 約2cm |
| 価格 | 900~1300円 |
透明感のある体は光の加減で虹色に輝き、尾ビレの上部は赤色に染まる非常に美しい種類です。デリケートなので水質の管理には十分に注意してください。
ナノストムス・ベックホルティ
| 学名 | Nannostomus beckfordi |
| 分布 | ガイアナ、ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約4cm |
| 価格 | 100~300円 |
カラシンの中でもペンシルフィッシュと呼ばれるグループの仲間で、細身の体に金色と黒色のラインが入ります。古くから親しまれているポピュラーな種類で、導入時にさえ気を付ければ飼育も容易です。
中大型のカラシン
ロングノーズクラウンテトラ
| 学名 | Distichodus lusosso |
| 分布 | コンゴ、アンゴラ(コンゴ川) |
| 体長 | 約50cm |
| 価格 | 3500~10000円 |
口吻部が長く伸長することが特徴で、体色はオレンジ色を基調に各ヒレが赤色になり、黒色の6本の横縞が入ります。成長とともに気性が荒くなるので単独飼育が基本です。
イエローピンクテールカラシン
| 学名 | Chalceus erythrurus |
| 分布 | ブラジル、ガイアナ、コロンビア、ベネズエラ |
| 体長 | 約20cm |
| 価格 | 900~1100円 |
腹ビレと尻ビレが黄色くなり、尾ビレはピンク色に染まる奇麗な種類です。同種間では小競り合いをしやすいので、混泳させる場合はある程度まとまった数を飼育すると良いでしょう。
ブラックコロソマ
| 学名 | Colossoma macropomum |
| 分布 | ペルー(アマゾン川) |
| 体長 | 約100cm |
| 価格 | 2800~3800円 |
大きいものは体長1mを超える大型の種類で、幼魚期の体色は明るい色をしていますが、成長とともに名前の通り黒色に変化していきます。丈夫なので設備さえ整えられれば飼育自体は容易です。
レッドコロソマ
| 学名 | Piaractus brachypomus |
| 分布 | ブラジル、コロンビア |
| 体長 | 約50cm |
| 価格 | 850~1200円 |
銀色の体色を基調に、下アゴから尻ビレにかけてが赤色に染まります。ピラニアとよく似ていますが、本種は植物食性が強い雑食性で、性格も比較的温厚です。
ピラニアナッテリー
| 学名 | Pygocentrus nattereri |
| 分布 | アマゾン川全域 |
| 体長 | 約30cm |
| 価格 | 400~1000円 |
ピラニアの中ではポピュラーな品種で、緑色を帯びたような銀色の体色を基調に、腹側が赤色に染まります。危険生物と名高いピラニアですが、本種は臆病な性格をしており複数で飼育することが基本です。
カラープロキロダス
| 学名 | Semaprochilodus insignis |
| 分布 | ブラジル(アマゾン川) |
| 体長 | 約30cm |
| 価格 | 1000~3000円 |
体色は銀色で腹ビレは赤く、尾ビレには黄色と黒色のラインが入ります。植物食性が強いので、コケ取り生体として大型魚のタンクメイトに採用されることも多い種類です。
ゴライアスタイガー
| 学名 | Hydrocynus goliath |
| 分布 | コンゴ(コンゴ川) |
| 体長 | 約150cm |
| 価格 | 8000~14000円 |
体長1mを超える大型種で、大きく鋭い歯を持つことが特徴です。巨体に見合わず神経質な面を持ち、餌が不足するとすぐに痩せてしまうので注意してください。
初心者におすすめのカラシンTOP3
カラシンは全体的にそれほどデリケートな魚種ではないので、熱帯魚飼育の入門にも適しています。ここでは、特に飼育しやすい初心者にもおすすめのカラシンをご紹介します。
第1位 ネオンテトラ・カージナルテトラ
どちらも小型カラシンだけでなく、熱帯魚全体を見渡した際の代表的な種類です。環境適応力が高くて丈夫なために飼育しやすく、安価で見栄えもすることから、入門には最適な条件を満たしています。これらの性質から、両者は水槽立ち上げ時のパイロットフィッシュとして選択されることも多いです。
第2位 レッドファントムテトラ
赤色の体色が水草との混泳で良く映え、安価で丈夫なことから入門に適しています。性格も温厚なので混泳相性も良く、水草と絡めた水槽レイアウトを色々と試してみるのも良いでしょう。本種は同種同士でフィンスプレッディングが見られることも魅力です。
第3位 ラミーノーズテトラ
頭部と体のコントラストが美しく群れを形成しやすいので、本種を水草水槽で群永させるだけでも大変見栄えのするアクアリウムに仕上がります。水質にうるさいこともなく、餌も何でもよく食べてくれるので飼育しやすい種類です。
カラシン(小型)の飼育方法
カラシンは種類が多く、小型種と中型種以上では飼育法が大きく異なります。ここでは、飼育しやすい小型種に絞って飼育方法などをご紹介します。
水温・水質

出典:イラストAC
小型カラシンの飼育に適した水温は24~28℃前後です。低水温だと「白点病」のリスクが上昇するので、冬はヒーターで加温して通年で25℃以上を保った方が良いでしょう。水質はpH6.0~7.5程度の弱酸性から中性付近を保てば問題ありません。硬度は軟水を好みますが、それほど神経質な魚種ではないので、カルキ抜きを忘れなければ水道水を調整する必要はありません。
水槽サイズ・フィルター

出典:イラストAC
小型カラシンは最大でも4cm程度にしか成長しないので、30cmクラスの水槽から飼育することが可能です。フィルターについては、小型カラシンを含む小型魚のみを飼育するのであれば、外掛け式などの形式でも十分です。ただし、きちんと水槽のサイズ(水量)に適合したものを導入してください。
レイアウト(底砂・アクセサリー)

出典:イラストAC
小型カラシンは基本的に臆病な性格をしているので、水草やシェルターなどで隠れられる場所を用意してあげた方が落ち着く傾向にあります。底床材は砂・砂利・セラミックスなど何でも良く、水草と混泳させるならソイルを使用しても良いでしょう。小型カラシンは上層から中層を泳ぐので、レイアウトの際は遊泳スペースを圧迫しないように配置してあげてください。
カラシンの餌
小型カラシンの餌は、同種用に配合された人工飼料が市販されているので、それで管理するのが容易です。それに加えて、たまに冷凍アカムシなどの生餌を与えてあげると、栄養バランスの面でも健全な成長が望めます。食べ残しが生じると水質の悪化を加速させてしまうので、給餌量には注意してください。
カラシンの混泳
小型カラシンは混泳相性が良い熱帯魚で、様々な魚種と混泳が可能です。ここでは、小型カラシンの混泳についてご紹介します。
同種・近縁種との混泳

出典:写真AC
同種・近縁種とは基本的に問題なく混泳が可能です。野生下では群永することで身を守っているので、むしろ複数で飼育した方がストレスの少ない環境になります。逆に、あまりにも少ない個体数を混泳させると、小競り合いをする傾向にあるので注意してください。また、小型カラシンの中でも「ブルーテトラ」などは縄張り意識が強く、混泳魚を攻撃することがあります。そのような種類と混泳させたい場合は、ブルーテトラなどの気性が荒い種類よりも、他の温厚な種類の数を多く入れるなど、力関係のバランスを取るようにすると良いでしょう。
他種との混泳

出典:写真AC
小型カラシンは他種との混泳相性も良好です。プレコやコリドラス、オトシンクルスなど多くの小型魚と相性が良く、水草などで隠れ場所を作ればディスカスなどの中型魚との混泳もできます。さらに、エビ類や貝類などとも混泳相性は良好です。ただし、他種と混泳させる場合はサイズ差に注意してください。ディスカスなどの中型魚の場合でも、小型カラシンが育ち切っていないと捕食される危険性が高いです。それから、大型魚には餌とみなされてしまうので、基本的に混泳はできません。
カラシンの繁殖
小型カラシンと一口に言っても繁殖の方法は種類によって異なります。ここでは、ネオンテトラを例に挙げてご紹介します。まず、繁殖させるためには繁殖用の水槽を用意し、そこに1匹のオスに対して2~3匹のメスを入れます。繁殖用の水槽には卵を親魚から保護するために、ネットを張ったり、ウィローモスなどの水草を敷き詰めておいてください。ネオンテトラはばら撒き型の産卵形態をとるので、産卵が確認されたら親魚は隔離して卵と産まれてくる稚魚を保護しましょう。誕生直後の稚魚は非常に小さいので、プランクトンですら食べることが困難です。ふ化直後~4日間程度は溶いた卵黄を与え、その後はインフゾリアなどのプランクトン類を与えてください。ネオンテトラのような代表種でも、繁殖はかなり難しいとされています。
カラシンの気をつけたい病気
熱帯魚の飼育において病気は付き物です。ここでは、カラシンについて気を付けるべき病気をご紹介します。
ネオン病
「カラムナリス菌」に感染することで発症する病気で、初期症状として魚体が白化して病状が進むと出血班が現れ、やがて衰弱死してしまいます。治療は病魚を隔離したうえで、「グリーンFゴールド」や「観パラD」などの魚病薬を用いて薬浴することにより行います。
白点病
白点病は熱帯魚の代表的な病気で、原因は水中に常在している「ウオノカイセンチュウ」という寄生虫に寄生されることで発症します。症状としては魚体に白色の斑点が現れ、体をあちこちに擦り付けるようにして泳ぐなどが挙げられます。治療は水温を30℃程度にまで上げたうえで、「グリーンFリキッド」や「ニューグリーンF」などの魚病薬で薬浴させることにより行います。
尾ぐされ病
原因はネオン病と同様に「カラムナリス菌」で、発症すると尾ビレを中心に各ヒレの先端が白く濁り、その周囲が充血するなどの症状が見られる病気です。重篤化するとヒレが裂け、溶けるようにして喪失していき、やがて衰弱死してしまいます。病原菌が同一なので、治療法はネオン病に準拠します。
カラシンを飼育して理想のアクアリウムを演出しよう!
カラシンは淡水魚の一大グループで、中にはネオンテトラやカージナルテトラなどのアクアリウムで飼育される代表的な熱帯魚も所属しています。小型の種類を中心に色鮮やかなものが多いので、アクアリウムの主役としても脇役としても水槽を賑わせてくれます。ぜひ、カラシンを飼育して理想のアクアリウム作りにチャレンジしてみてください。































![(熱帯魚)ネオンテトラ(10匹) 本州・四国限定[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/41jvbh5PgTL._SL500_.jpg)
![(熱帯魚)カージナルテトラ(ブリード)(10匹) 本州・四国限定[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GT9DNissL._SL500_.jpg)
![(熱帯魚)レッドファントム・ルブラ(ワイルド)(6匹) 本州・四国限定[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51UmjI5Ly1L._SL500_.jpg)