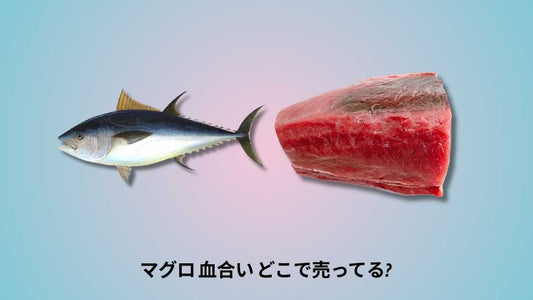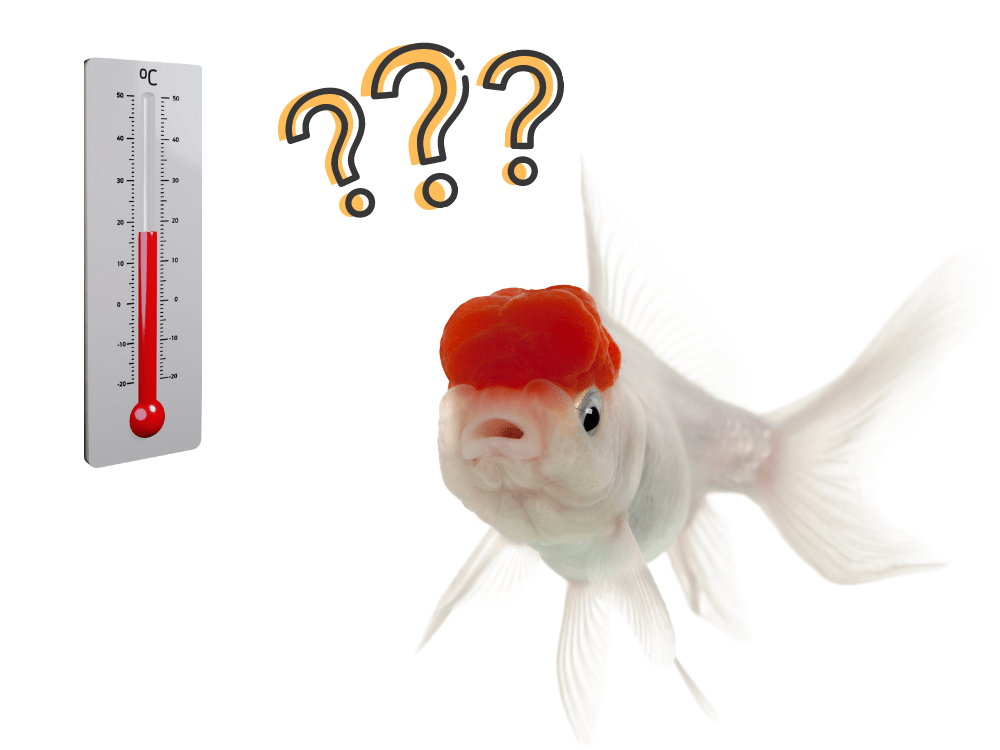
金魚飼育に最適な水温(適温)は?夏・冬の水温変化を抑える方法とは
Share
金魚にとっての快適な水温は?
 金魚は幅広い水温下で生存可能ですが、金魚にとって活動に適した快適な水温となると限られてきます。 金魚にとって快適な水温は20~26℃前後で、特に23~25℃位が最適だと言われています。金魚は環境さえ整えれば、夏や冬もヒーターなどの温調機器を使用せずに飼育可能です。 しかし、快適な水温を外れると活性が低下し、餌食いが悪くなるなど行動の変化が見られます。 給餌など日常のコミュニケーションに重きを置きたい場合、適温を外れる時期はその楽しみが減ってしまうので、飼育目的によって年間を通して保温するか否か決めると良いでしょう。
金魚は幅広い水温下で生存可能ですが、金魚にとって活動に適した快適な水温となると限られてきます。 金魚にとって快適な水温は20~26℃前後で、特に23~25℃位が最適だと言われています。金魚は環境さえ整えれば、夏や冬もヒーターなどの温調機器を使用せずに飼育可能です。 しかし、快適な水温を外れると活性が低下し、餌食いが悪くなるなど行動の変化が見られます。 給餌など日常のコミュニケーションに重きを置きたい場合、適温を外れる時期はその楽しみが減ってしまうので、飼育目的によって年間を通して保温するか否か決めると良いでしょう。 金魚が耐えられる水温は?
金魚は屋外飼育できることからも分かる通り、水温に対する適応力が高い魚です。ここでは、金魚の具体的な水温耐性について詳しく解説します。
夏の高水温
 金魚の祖先は、温帯地域に分布するフナであることも手伝って、夏場の高水温には比較的強いです。 高温側は35℃程度までは耐えられると言われていますが、当然ながら金魚にとって住み良い環境ではありません。
長期にわたって同水温帯で飼育していると調子を崩す可能性が高いので、必要に応じて冷却ファンなどを導入する必要があります。
また、高水温帯では酸素欠乏のリスクも上昇してしまいます。なぜなら、一般的に酸素などの気体は、水温が高くなるほど水中に溶け込める量が少なくなるためです。
このことからも、夏場の水温管理は重要で、金魚の健康を願うのなら、30℃を超えるような高水温下での飼育は避けた方が良いでしょう。
金魚の祖先は、温帯地域に分布するフナであることも手伝って、夏場の高水温には比較的強いです。 高温側は35℃程度までは耐えられると言われていますが、当然ながら金魚にとって住み良い環境ではありません。
長期にわたって同水温帯で飼育していると調子を崩す可能性が高いので、必要に応じて冷却ファンなどを導入する必要があります。
また、高水温帯では酸素欠乏のリスクも上昇してしまいます。なぜなら、一般的に酸素などの気体は、水温が高くなるほど水中に溶け込める量が少なくなるためです。
このことからも、夏場の水温管理は重要で、金魚の健康を願うのなら、30℃を超えるような高水温下での飼育は避けた方が良いでしょう。
冬の低水温
 低温側は0℃までは耐えられると言われています。ただし、水面が凍るくらいなら耐えられますが、水中まで氷結してしまうとその限りではないので注意してください。
言うまでもなく、金魚にとっては過酷な環境で、ここまで水温が低下すると冬眠してしまいます。金魚の冬眠を成功させるためには一定のノウハウが必要となるので、金魚の飼育自体に慣れていない方は、ヒーターを導入して保温することをおすすめします。
また、年間を通して金魚とのコミュニケーションを楽しみたい場合も同様です。
低温側は0℃までは耐えられると言われています。ただし、水面が凍るくらいなら耐えられますが、水中まで氷結してしまうとその限りではないので注意してください。
言うまでもなく、金魚にとっては過酷な環境で、ここまで水温が低下すると冬眠してしまいます。金魚の冬眠を成功させるためには一定のノウハウが必要となるので、金魚の飼育自体に慣れていない方は、ヒーターを導入して保温することをおすすめします。
また、年間を通して金魚とのコミュニケーションを楽しみたい場合も同様です。
外国産金魚と国産金魚の適水温の違い
 昨今の金魚ブームを反映し、最近では東南アジアなどでブリードされた金魚も輸入され、国内で流通しています。そういった外国産の、特に熱帯地域で育てられた金魚は、国産のものよりも低温耐性が低い傾向にあるので注意してください。
熱帯地域産の金魚の適水温は熱帯魚と同様、 25℃前後だと言えます。しかし、どこで育とうとも金魚は金魚。低水温に適応する能力は有しているため、東南アジア産の個体でもゆっくりと日本の気候に適応させれば、国産のものと同じように飼育できるようになります。
東南アジア産の金魚を温調機器なしで飼育したい場合、まずは適水温が通年で保たれた環境で、体力がつくまで飼育しましょう。それから、徐々に低い温度の水にさらすようにしていけば慣れてくれる場合も多いです。
昨今の金魚ブームを反映し、最近では東南アジアなどでブリードされた金魚も輸入され、国内で流通しています。そういった外国産の、特に熱帯地域で育てられた金魚は、国産のものよりも低温耐性が低い傾向にあるので注意してください。
熱帯地域産の金魚の適水温は熱帯魚と同様、 25℃前後だと言えます。しかし、どこで育とうとも金魚は金魚。低水温に適応する能力は有しているため、東南アジア産の個体でもゆっくりと日本の気候に適応させれば、国産のものと同じように飼育できるようになります。
東南アジア産の金魚を温調機器なしで飼育したい場合、まずは適水温が通年で保たれた環境で、体力がつくまで飼育しましょう。それから、徐々に低い温度の水にさらすようにしていけば慣れてくれる場合も多いです。
金魚にとっての最適な水温を保つ方法
水温は温調機器を導入する他に、水槽の設置場所を工夫するなどの措置を取ると、より安定しやすくなります。ここでは、適水温を保つための方法をご紹介します。
設置場所を十分に考慮する
 水槽など金魚の飼育容器の設置場所は、適水温を保つうえで重要です。なぜなら、飼育水の温度は気温の変化に連動することに加え、日光の影響も多分に受けるからです。
気温の変化が大きい場所や日光が当たる場所に設置すると、その分だけ適水温の維持が困難になるので注意してください。水槽に日光を当てないことは、コケの発生抑制の観点からも重要です。
基本的に水槽は1日の気温の変動が少なく、日光が当たらない場所に設置してください。人がよく居る部屋などは、空調によって適水温を保ちやすく、鑑賞するうえでも都合が良いのでおすすめです。
水槽など金魚の飼育容器の設置場所は、適水温を保つうえで重要です。なぜなら、飼育水の温度は気温の変化に連動することに加え、日光の影響も多分に受けるからです。
気温の変化が大きい場所や日光が当たる場所に設置すると、その分だけ適水温の維持が困難になるので注意してください。水槽に日光を当てないことは、コケの発生抑制の観点からも重要です。
基本的に水槽は1日の気温の変動が少なく、日光が当たらない場所に設置してください。人がよく居る部屋などは、空調によって適水温を保ちやすく、鑑賞するうえでも都合が良いのでおすすめです。
金魚の水槽の水温を上げるにはヒーターが便利
 水槽の設置場所を工夫しても、冬場の低水温の抑止には限界があることでしょう。そこで便利なのが、水槽用ヒーターの存在です。ヒーターを入れておけば、年間を通した適温の維持が格段に容易になります。
水槽用ヒーターには温度調節機能があるものとないものがあり、前者は白点病治療の際にも役立つのでおすすめです。その分やや高価ですが、万一に備えておくことは無駄ではありません。
また、アクアリウムにおけるヒーターは基本的に消耗品という考え方で、故障に備えて予備も必ず用意しておきましょう。
それから、ヒーターは必ず水槽サイズ(運用水量)に対応したものを導入してください。対応しているサイズと違うものを入れてしまうと、十分な加温効果を得られないなどの不利益が生じてしまいます。
水槽の設置場所を工夫しても、冬場の低水温の抑止には限界があることでしょう。そこで便利なのが、水槽用ヒーターの存在です。ヒーターを入れておけば、年間を通した適温の維持が格段に容易になります。
水槽用ヒーターには温度調節機能があるものとないものがあり、前者は白点病治療の際にも役立つのでおすすめです。その分やや高価ですが、万一に備えておくことは無駄ではありません。
また、アクアリウムにおけるヒーターは基本的に消耗品という考え方で、故障に備えて予備も必ず用意しておきましょう。
それから、ヒーターは必ず水槽サイズ(運用水量)に対応したものを導入してください。対応しているサイズと違うものを入れてしまうと、十分な加温効果を得られないなどの不利益が生じてしまいます。
水温を下げるにはクーラーやファンを使う
 夏場に水温を下げたい時は、冷却ファンや水槽用クーラーの出番です。冷却ファンは比較的安価で設置も容易と手軽に導入できる点が魅力ですが、言ってしまえば扇風機そのものなので冷却能力はそれなりです。
対してクーラーの方は、熱交換器などを用いてしっかりと冷やすため冷却能力に優れますが、その分だけ高価です。
水槽においては温めて保温するよりも、冷やして保温する方がコストや手間がかかるため、夏場の高水温が問題になる場合は、エアコンを用いて室温ごと管理する方法もあります。
夏場に水温を下げたい時は、冷却ファンや水槽用クーラーの出番です。冷却ファンは比較的安価で設置も容易と手軽に導入できる点が魅力ですが、言ってしまえば扇風機そのものなので冷却能力はそれなりです。
対してクーラーの方は、熱交換器などを用いてしっかりと冷やすため冷却能力に優れますが、その分だけ高価です。
水槽においては温めて保温するよりも、冷やして保温する方がコストや手間がかかるため、夏場の高水温が問題になる場合は、エアコンを用いて室温ごと管理する方法もあります。
断熱シートや照明の種類にも気を配ろう
 飼育水の保温には断熱シートの活用も効果的です。特に、外部フィルターを使用している場合、冬場は飼育水がフィルター内を通過している間に冷やされてしまいます。
そこで、フィルターを断熱シートで覆えば、冷たい外気の影響を軽減できるため、飼育水の保温効果が得られるというわけです。同様の理由で、水の外に出ているホースやパイプなどにも断熱シートを施せば、より効果が上がります。
また、夏場の水温上昇が気になる時は、照明の種類にも注目してみてください。水槽用照明はLED・蛍光灯・メタハラなどの種類があり、それぞれ点灯の際の発熱量に差があります。
一般的にはLED照明が最も発熱量が少ないと言われているので、水温上昇が心配ならばLED照明を導入すると良いでしょう。
飼育水の保温には断熱シートの活用も効果的です。特に、外部フィルターを使用している場合、冬場は飼育水がフィルター内を通過している間に冷やされてしまいます。
そこで、フィルターを断熱シートで覆えば、冷たい外気の影響を軽減できるため、飼育水の保温効果が得られるというわけです。同様の理由で、水の外に出ているホースやパイプなどにも断熱シートを施せば、より効果が上がります。
また、夏場の水温上昇が気になる時は、照明の種類にも注目してみてください。水槽用照明はLED・蛍光灯・メタハラなどの種類があり、それぞれ点灯の際の発熱量に差があります。
一般的にはLED照明が最も発熱量が少ないと言われているので、水温上昇が心配ならばLED照明を導入すると良いでしょう。
水温計で金魚水槽の水温をしっかりとチェックする
 水温は見た目には分からないので、水温計を用意しておくことも重要です。水温計は可能なら常設し、毎日の餌やりの際にでもチェックする習慣を付けておくと良いでしょう。
そうすれば温調機器の故障といったアクシデントをいち早く察知し、金魚が調子を崩す前に対処することも可能になります。
特に、冬場にヒーターが故障して、いきなり低水温にさらされてしまうと金魚といえども危険なので、気を付けてあげてください。
水温は見た目には分からないので、水温計を用意しておくことも重要です。水温計は可能なら常設し、毎日の餌やりの際にでもチェックする習慣を付けておくと良いでしょう。
そうすれば温調機器の故障といったアクシデントをいち早く察知し、金魚が調子を崩す前に対処することも可能になります。
特に、冬場にヒーターが故障して、いきなり低水温にさらされてしまうと金魚といえども危険なので、気を付けてあげてください。
金魚の飼育水温と餌の与え方の関係性
適水温の時期は多めに与える
 飼育水が金魚にとって適温になる時期は金魚の活性も上がり、それと共に必要とする餌の量も増えるので多めに給餌してください。
特に、ヒーターを使用しない場合は、適水温の時期にしっかりと成長して体力が充実した状態になっていないと、冬場を超すことが困難になってしまいます。
ここで注意してほしいことは、餌を多めに与えると言っても1回の給餌量を増やすのではなく、1日の給餌回数を増やす点です。なぜなら、1回の量を増やしても食べきれずに残してしまったり、逆に食べ過ぎて消化不良を起こす恐れがあるからです。
適温期は1日に2~4回程度を目安に、それぞれ数分で食べきれるだけの量を与えるようにしてください。
飼育水が金魚にとって適温になる時期は金魚の活性も上がり、それと共に必要とする餌の量も増えるので多めに給餌してください。
特に、ヒーターを使用しない場合は、適水温の時期にしっかりと成長して体力が充実した状態になっていないと、冬場を超すことが困難になってしまいます。
ここで注意してほしいことは、餌を多めに与えると言っても1回の給餌量を増やすのではなく、1日の給餌回数を増やす点です。なぜなら、1回の量を増やしても食べきれずに残してしまったり、逆に食べ過ぎて消化不良を起こす恐れがあるからです。
適温期は1日に2~4回程度を目安に、それぞれ数分で食べきれるだけの量を与えるようにしてください。
適温を外れる時期は消化に良いものを少なめに
 晩秋から春先など低水温期は金魚の活性が低下し、必要な餌の量も減少します。また、活性の低下に伴い消化能力も弱くなる傾向にあるので、なるべく消化しやすい餌を与えた方が良いです。
目安となる水温は20℃で、この水温を下回ると消化能力が低下すると言われているため、餌の切り替えを考えてください。
低水温期の給餌回数の目安は1日に1~2回で、やはり数分で食べきれるだけの分量を与えましょう。
晩秋から春先など低水温期は金魚の活性が低下し、必要な餌の量も減少します。また、活性の低下に伴い消化能力も弱くなる傾向にあるので、なるべく消化しやすい餌を与えた方が良いです。
目安となる水温は20℃で、この水温を下回ると消化能力が低下すると言われているため、餌の切り替えを考えてください。
低水温期の給餌回数の目安は1日に1~2回で、やはり数分で食べきれるだけの分量を与えましょう。
冬眠させる場合は餌切りを行う
 屋外飼育などで冬眠させる場合は、徐々に餌の量を減らしていき、水温が10℃ほどにまで低下したら完全に餌を与えない 餌切りを行ってください。冬眠中は餌を与えても食べずに、いたずらに水を汚すだけなので給餌する必要はありません。
それに、冬眠中はエネルギーをほとんど消費しないため、十分に育って体力のある金魚なら数カ月間、絶食状態になっても生存可能です。
逆に言うと、十分に成長していなかったり、冬眠前に調子を崩してしまった個体は冬眠に耐えられないケースが多いため、適温に保温された環境で管理する必要があります。
給餌を再開するタイミングは水温が上がって泳ぎだしてからで、その時もいきなり通常どおりの量を与えず少量に留め、徐々に量を増やしてください。
屋外飼育などで冬眠させる場合は、徐々に餌の量を減らしていき、水温が10℃ほどにまで低下したら完全に餌を与えない 餌切りを行ってください。冬眠中は餌を与えても食べずに、いたずらに水を汚すだけなので給餌する必要はありません。
それに、冬眠中はエネルギーをほとんど消費しないため、十分に育って体力のある金魚なら数カ月間、絶食状態になっても生存可能です。
逆に言うと、十分に成長していなかったり、冬眠前に調子を崩してしまった個体は冬眠に耐えられないケースが多いため、適温に保温された環境で管理する必要があります。
給餌を再開するタイミングは水温が上がって泳ぎだしてからで、その時もいきなり通常どおりの量を与えず少量に留め、徐々に量を増やしてください。
水温差が大きいと金魚が体調を崩すことも
 金魚は幅広い水温に適応できますが、それは季節の変わる速度がある程度ゆっくりとした場合に限られます。1日の水温差が大きいと、金魚でも適応できずに体調を崩してしまうことがあり、水温差に起因する体調不良は 水温ショックと呼ばれています。
水温ショックによる症状は様々なものがあります。軽度なら底の方で動かなくなるなどの症状が出た後じきに回復しますが、重度になると病気にかかってしまったり、最悪の場合は急死する恐れもあるので注意が必要です。
水温ショックによってかかりやすくなる病気としては、 白点病やエロモナス症が挙げられます。
また、水温ショックは消化不良を誘発することもあり、そこから転覆病などに発展する危険もあるので、1日レベルでの水温の変動には十分に注意を払う必要があります。
金魚は幅広い水温に適応できますが、それは季節の変わる速度がある程度ゆっくりとした場合に限られます。1日の水温差が大きいと、金魚でも適応できずに体調を崩してしまうことがあり、水温差に起因する体調不良は 水温ショックと呼ばれています。
水温ショックによる症状は様々なものがあります。軽度なら底の方で動かなくなるなどの症状が出た後じきに回復しますが、重度になると病気にかかってしまったり、最悪の場合は急死する恐れもあるので注意が必要です。
水温ショックによってかかりやすくなる病気としては、 白点病やエロモナス症が挙げられます。
また、水温ショックは消化不良を誘発することもあり、そこから転覆病などに発展する危険もあるので、1日レベルでの水温の変動には十分に注意を払う必要があります。
金魚飼育は水温管理がカギ!
 金魚は幅広い水温に適応できますが、そのあらゆる範囲で元気に過ごせるわけではありません。適水温を外れてしまうと活性が低下し、餌食いが悪くなるなど行動が変化します。
活性が低くなると消化能力も低下するため、通年で保温しない場合は、季節によって餌の種類や給餌方法も考える必要が出てきます。
また、1日の水温差が大きいと体調を崩すこともあるので、金魚だから大丈夫と過信せずに、きちんと水温を管理して健康的に飼育してあげてください。
金魚は幅広い水温に適応できますが、そのあらゆる範囲で元気に過ごせるわけではありません。適水温を外れてしまうと活性が低下し、餌食いが悪くなるなど行動が変化します。
活性が低くなると消化能力も低下するため、通年で保温しない場合は、季節によって餌の種類や給餌方法も考える必要が出てきます。
また、1日の水温差が大きいと体調を崩すこともあるので、金魚だから大丈夫と過信せずに、きちんと水温を管理して健康的に飼育してあげてください。
スポンジフィルター人気ランキングTOP10!お手入れ方法やろ過能力の比較も!