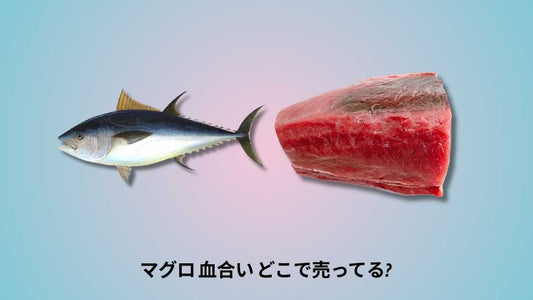ヒメダカから始めるアクアリウム!飼育方法や餌の種類、繁殖法など
Share
アイキャッチ画像出典:写真AC
ヒメダカってどんな魚?
ヒメダカは原種メダカの突然変異体を固定した品種で、改良品種の中で最も古いものと言われています。まずはヒメダカについて特徴や寿命などをご紹介します。
バタフライフィッシュ(パントドン)の特徴や生態、飼育方法など
ヒメダカの特徴
出典:写真AC
ヒメダカは突然変異体の固定に成功した品種で、原種が持つ黒色の色素が抜けているため、体色は黄色からオレンジ色に見えます。体長は原種と変わらず3~4cmほどで、もともと日本に生息しているだけあり、急変さえ避ければ幅広い水温・水質に適応できる丈夫な魚種です。
食性は雑食性で、口に入るものなら何でも食べてくれるため餌付けも容易で飼育しやすく、アクアリウムの入門種としても最適です。
ヒメダカの寿命
出典:写真AC
メダカの寿命は自然環境下では1年ほどですが、 飼育下では2~3年程度と言われています。病気に気を付けて飼育環境を上手に管理できれば、5年以上生きる例も報告されています。
それほど寿命が長いわけではありませんが、ヒメダカを含むメダカ類は水槽内での繁殖も可能なので、その気になれば長く楽しめます。
/
改良品種としてのヒメダカ
出典:写真AC
先に少し触れましたが、ヒメダカは原種であるミナミメダカまたはキタノメダカの突然変異体を固定した品種です。原種が保有していた黒色の色素を失っているため、体色は黄色からオレンジ色をしています。
ヒメダカの歴史は古く、メダカの飼育が文献に登場する時期が18世紀なのですが、この頃には既に原種と共に飼育されていたと言われています。また、現在流通している様々な改良品種の元になった品種でもあるので、ヒメダカが果たした役割は大きいです。
ラミレジィの種類や飼育・繁殖方法!おすすめの餌、混泳相性など
ヒメダカの飼育方法
ヒメダカの飼育は特別難しいことはありません。しかし、強い水流を嫌い、身を隠せる場所があった方が落ち着く魚種であることは知っておいてください。ここでは、ヒメダカの飼育方法をご紹介します。
ヒメダカ飼育に適した容器
水槽
ヒメダカを屋内で飼育する場合は水槽が適しています。ヒメダカは小型なので小型水槽から飼育ができますが、水量に対して適した個体数があるため、過密状態にならないよう注意してください。
ヒメダカクラスの小型魚の場合、 体長1cmにつき水1Lが目安と言われています。また、ヒメダカは外敵に対しては神経質です。水槽のような周囲から丸見えの環境ではストレスを感じる傾向にあるので、水草やシェルターで隠れられる場所を作ってあげてください。
鉢
屋外で飼育する場合は睡蓮鉢のような大型の容器が適しています。ある程度の水量を確保しつつ、ホテイ草などの浮草で隠れ家を作ってあげれば、フィルターなどの外部機器なしでもヒメダカは元気に育ちます。
屋外飼育の場合は日光が当たる場所に設置することがポイントで、そうすることでプランクトンの発生を促せるので、餌もあまり与えずに済みます。
その他容器
多くのヒメダカを飼育したい時は、プラ舟や埋め込み池などの容器が向いています。これらの容器で管理する時も鉢の場合と同様、日当たりの良い場所に設置すると良いでしょう。
ただし、自然災害に対しては備えが必要で、屋内に避難させるための水槽などは用意しておくことをおすすめします。
/
フィルター
ヒメダカはあまり水を汚さないので、フィルターはどのような形式でも問題ありません。価格とメンテナンス性を考慮すると、外掛けフィルターや上部フィルターが有力な候補です。
ただし、強い水流は嫌うため、フィルターの排水やエアポンプからの空気によって速い流れが発生しないよう、配置や出力は調整してあげてください。
フィルターの排水が問題になるようでしたら、シャワーパイプやフローパイプなどの使用を視野に入れると良いでしょう。
水温・水質
ヒメダカの適温は23~28℃ほどです。生存自体は、5℃を少し下回る位から30℃を超えるほどまで可能ですが、低温では冬眠させる必要がありますし、あまり高温になると弱ってしまうので注意が必要です。
寒い時期はヒーターを使用すると良いです。また、水温によってメダカの餌食いなども変わってくるので、水温計は必ずつけておきましょう。
水質に関しては、弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く適応できます。ヒメダカは適応力が高い魚種なのですが、あまりにアルカリ性側や酸性側に傾くと調子を崩してしまうので、水質に影響を与える底床材の導入や水換えの頻度には注意してください。
/
ヒメダカの餌
前述の通り、口に入る大きさの物であれば何でも食べてくれるので、メダカ用に販売されている人工飼料だけでも飼育できます。
しかし、特に繁殖を狙う場合などは栄養価の高いものを食べさせたほうが良いため、たまにで良いので冷凍アカムシなどの生餌も与えると、より健康的に成長します。
屋外飼育の場合は、グリーンウォーター(青水)で管理すると繁殖もスムーズです。
ヒメダカの繁殖方法
出典:写真AC
ヒメダカを繁殖させるには、まずオスとメスを用意しなければなりません。個体同士の相性の問題があるため、オス1匹に対して複数のメスを用意すると良いでしょう。
繁殖させる容器には、卵を産み付ける産卵床が必要です。産卵床にはホテイ草などの水草や、ナイロンなどを束ねた人工物が市販されているので、それらを入れておきましょう。後は、飼育環境を適切な状態に保ちつつ、普通に飼育していれば産卵にまで至ります。
産卵が確認されたら卵は食べられないよう、親魚から隔離して保護しましょう。隔離した卵はプラケースなどに入れ、薄いメチレンブルーで殺菌しておくと確実です。
ふ化した稚魚は非常に小さいので、餌に注意してください。稚魚用に微細な餌を用意しておかないと、口に餌が入らないがゆえに摂食できず餓死してしまいます。
稚魚の餌は粒径が小さい人工飼料でも良いですが、 ゾウリムシなどのプランクトン類がおすすめです。熱帯魚飼育で定番のブラインシュリンプでは、誕生直後の針子には大きすぎるので注意してください。
/
ヒメダカの混泳
出典:写真AC
ヒメダカは温厚な魚種なので混泳相性は良好です。色々な生物と混泳が可能なので、そういった意味でもアクアリウムの入門に向いています。ここでは、ヒメダカの混泳についてご紹介します。
ヒメダカと他の種類のメダカは一緒に入れたらダメなの?
結論から言えば、ヒメダカと他の品種のメダカを混泳させても問題ありませんが、交雑には注意が必要です。ヒメダカは原種に近い品種で、他の品種は潜性(劣勢)の形質を固定したものが多いです。
そのため、ヒメダカと交配すると子の世代は、その品種を足らしめている形質を失った個体が多く生まれてしまうので、他の品種の形質を保存したいのであれば、混泳は避けた方が良いです。
ヒメダカと混泳相性のいい生物
ヒメダカは大人しい魚種なので、同じくらいの大きさで温厚な魚種であれば、熱帯魚とも混泳可能です。例としては、小型コイ科魚類やコリドラスなどが挙げられます。
その他の生物では、貝類やエビ類とも相性が良く、ヒメタニシやミナミヌマエビ、ヤマトヌマエビなどとも混泳できます。ただし、グリーンウォーターで飼育したい場合、タニシなどを入れておくと水中の植物プランクトンを捕食してしまい、グリーンウォーターの維持が難しくなる点は留意しておいてください。
/
ヒメダカの注意したい病気
ヒメダカは基本的には丈夫な魚種なのですが、言うまでもなく飼育環境が不適切だと、調子を崩して病気になってしまうこともあります。ここでは、ヒメダカの飼育において、気を付けるべき病気をご紹介します。
水カビ病
真菌の1種である「水カビ」に寄生される病気です。ヒメダカの体に、白色の綿のように見える水カビが付着し、ヒメダカの体表組織から養分を吸収します。病気が進行して水カビがエラにまで及ぶと、窒息死する危険があるので早期に治療しなければなりません。
治療は「グリーンFリキッド」や「アグテン」などの魚病薬を用いた薬浴で行います。その際に、塩水浴を並行することも効果的です。水カビは郵送時のスレなど外傷があると寄生しやすくなるので、外傷の早期治癒が予防につながります。
尾ぐされ病
水中常在菌の1種である「カラムナリス菌」に感染することで発症する病気です。初期段階ではヒレが白く濁る程度ですが、病気が進行すると尾ビレを中心に各ヒレがボロボロに溶けてしまいます。
効果的な魚病薬は「グリーンFゴールド顆粒」や「観パラD」などが挙げられます。尾ぐされ病によってヒレが傷つくと、その患部に水カビが2次感染しやすくなるので早期治療が重要です。
針病・やせほそり病
メダカがよく陥る病気で、尾ビレをたたんで体をくねらせるようにして泳ぐ症状が出ます。餌を食べいるはずなのに体が痩せ、横から見ると針のような形状になるので「針病」や「やせほそり病」と呼ばれています。
この病気の原因ははっきりと分かっていませんが、交配が進んだ結果、内臓に先天的な障害がある場合や、水質の悪化などが考えられています。
それに伴い治療法も確立されていませんが、対処法としては消化に良い餌を与えたり、飼育環境を清浄に保つこと、メチレンブルーでの薬浴などが挙げられます。
ヒメダカは安価かつ丈夫で可愛いアクアリウムの入門種!
出典:写真AC
ヒメダカは数あるメダカの品種の中でも、最初期に作出された基本的な種類です。体色こそ昨今世間を騒がせている品種と比較すると地味なものの、安価かつ丈夫でメダカ特有の可愛らしさは他と変わりません。
ヒメダカを飼育することで、アクアリウムの基礎を繁殖に至るまでをも学ぶことが可能なので、これからアクアリウムを始めようとお考えの方に特におすすめできる魚種です。