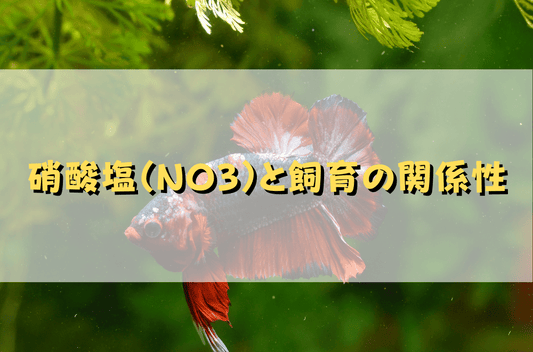【超入門】タコ釣りに必要なタックルや仕掛け!釣れやすい時期・時間帯は?
Share
日本各地にファンの多いタコ釣り。明石や東京湾などの船釣りが有名ですが、実は堤防など岸からも狙うことができるんです。専用の道具は必要ですが、難しい仕掛けやテクニックは必要ありません。本記事では初心者でも手軽に始めることができる 堤防からのタコ釣りについて解説していきます。
タコ釣りで狙えるタコの種類は?
タコ釣りで狙えるタコにはどんな種類がいるのでしょうか?代表的なものを3種類ご紹介します。
マダコ

マダコは北海道〜九州各地の沿岸に分布し、日本人には最も身近で馴染みの深いタコです。全長60cm、体重3kgほどにまで成長します。一般的に「タコ釣り」というと本種を狙った釣りを指し、本記事でもタコ釣りというとこのマダコ狙いという前提で話を進めていきます。
イイダコ

イイダコは大きくても30cmほどの小型のタコで、通常釣れるサイズは10〜20cmほどが多いです。北海道以南の日本沿岸各地に分布し、主に内湾の砂地に生息しています。白いものに興味を示す習性を持ち、らっきょうや脂身などを付けたテンヤで狙います。
イイダコ釣りについては詳しくは以下の記事をご覧ください。
ミズダコ

ミズダコは全長3m、体重50kgほどにまで成長する世界最大のタコで、北太平洋に広く分布し、日本では東北地方以北に生息しています。特に秋田県では生息数が多く、ミズダコを専門に狙った遊漁船が出ています。
タコ釣りの時期(シーズン)

タコ釣りは主に 5~10月頃の暖かい時期が適しており、特にハイシーズンは 6~9月頃です。サイズは小さめが多いですが、数釣りが期待できます。11月〜4月頃までの低水温期はタコが深場へ落ちてしまうため、岸からは釣れにくくなりますが、タコのサイズは大きくキロアップも期待できます。
また、冬場は他の釣り人のプレッシャーも少なく、狙いたいポイントを攻めやすいというメリットがあります。絶対数は少ないですが、一発大物を狙うなら冬にタコを狙うのも面白いかもしれません。
/タコ釣りにベストな時間は?

タコは夜行性の生き物なので、一番釣れやすい時間はズバリ夜です。ただし、夜間は暗いためヘッドライトが必須になりますし、根掛かりなどで仕掛けが切れた際に結び直すのに難儀します。また、足元が見えにくいので落水の危険性もあります。
そこでタコ釣り入門におすすめしたいのが、釣りのしやすい日中と、「朝まずめ」・「夕まずめ」の時間帯です。朝まずめは日の出前後1時間くらいの時間帯、夕まずめは日没前後1時間くらいの時間帯のことを指します。
夜行性のタコですが、日中でも釣れない訳ではありません。夜ほど活発に動き回らないというだけで、元々貪欲な生物なので餌を見つければガンガン食ってきます。初心者の方であれば安全性と釣りのしやすさを考えて、 朝まずめや夕まずめを中心に、まずは明るい時間帯からタコ釣りを始めるのがおすすめです。
タコ釣りで狙う場所(釣り場)

タコは岩陰や海草の中などに身を潜めていることが多いので、タコ釣りでは基本的に 障害物(ストラクチャー)周りを探るのが基本になります。特に 漁港はテトラポッドや根(海底の岩)、海草などのストラクチャーが多く、カニや貝などタコの餌になる生物も多いため一級ポイントとなります。
また、意外と見落としがちなのが堤防の際です。つい遠投して広範囲を探りたくなりますが、漁港の堤防や岸壁はそれ自体が大きなストラクチャーであり、様々な生物が潜んでいます。足元も忘れずに探ってみましょう。
釣り場選びのポイントとして注意したいのは、タコは 真水を嫌う性質があるということです。汽水域や河口周りのポイントはタコを狙いにくくなるので避けましょう。また、雨が降って一時的に塩分濃度が下がるときなどはタコは深場へ逃げてしまうので注意しましょう。
/タコ釣りの仕掛け
ここからはタコ釣りの仕掛けについて見ていきましょう。タコ釣りでは主に タコエギ、タコテンヤ、タコジグの3種類の仕掛けがあります。それぞれの仕掛けの特徴と釣り方について解説していきます。
タコエギ

特徴
タコエギはエビの形に似せたタコ専用の疑似餌(ルアー)です。 3種類の仕掛けの中では近年最もポピュラーであり、タコのサイズを問わず数釣りが見込めるため、初心者の方にはまずこのタコエギをおすすめします。
よく似た形でイカ釣り(エギング)用の「エギ」と呼ばれるルアーがありますが、タコエギは底を重点的に探るためにイカ用のエギよりも沈下速度が速く、底を取りやすい設計になっています。
また、カンナ(針)部分がイカ用のエギよりも太く大きくなっており、タコが海底にへばりついても曲げられることがないようになっています。サイズは3.5号を基準とし、カラーは赤・オレンジ・白などが定番になります。
使い方
基本的な使い方はタコエギをキャストして底まで沈め、海底をずる引きして誘っていきます。タコエギを軽くしゃくったり小刻みにシェイクさせてアピールするのも効果的ですが、底からタコエギを浮かせすぎないようにするのがポイントです。あくまでベタ底を意識してタコエギを操作しましょう。
タコが乗ったら根掛かりしたように重くなるので、一気にタコを底から引き剥がして巻き上げましょう。タコエギはキャストするため、初心者の方はスピニングタックルが扱いやすくておすすめです。
タコエギについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。
タコテンヤ

特徴
タコテンヤはオモリと大きなフックがついた板に餌を結びつけてタコを誘い出す仕掛けです。餌はアジやイワシなどの小魚、カニのほか豚の背脂なども使われたりします。カニを模したゴム製のソフトルアーを使うこともあります。重さは15号(約56g)程度が基準です。
餌を別途用意する手間とコストがかかりますが、餌を使うため他の仕掛けよりもタコの食いつきは良くなります。タコエギで反応が悪い時などはタコテンヤの出番になります。また、タコエギに比べ大型のタコが釣れやすいため、 数よりも大型狙いに絞るならタコテンヤがおすすめです。
使い方
基本的な使い方はタコエギとほぼ同じで、キャストしてから底をずる引きしていき、たまに小刻みにシェイクを入れて誘います。タコテンヤでもきっちりとベタ底を意識し、仕掛けが底から浮かないように注意しましょう。キャストする仕掛けなので、初心者の方はやはりスピニングタックルがおすすめです。
タコジグ

特徴
タコジグは小型のタコを模したような見た目の仕掛けです。スカート部分がヒラヒラと舞ってタコにアピールします。針が四方に伸びているため、タコのかかりは良いですが、同時に根掛かりのリスクも高くなります。
使い方
タコジグはキャストしてずる引きするとすぐに根掛かりしてしまうため、基本的には足元に落として細かくシェイクして誘うのがメインの使い方になります。
また、タコジグ同士を連結することもでき、2〜3個を縦につなげて使う場合もあります。こうすることで海底から少し浮いた場所も探ることができ、海底に潜むタコと同時に、岸壁の側面に張り付いているタコにもアピールすることができます。
タックルに関しては手返しよく釣りができるベイトタックルが適していますが、キャストして広範囲を探るタコエギやタコテンヤとの併用を考えてスピニングタックルを使っても問題ありません。ベイトタックルでもキャストはできますが、少々コツが要るため初心者の方にはおすすめできません。
タコ釣りに使う竿(ロッド)

タコ釣りに使うロッドは、タコが吸盤で岩などに張り付いているのを無理矢理引き剥がすために、強靭なものが必要になります。長さは7ft(約2.1m)程度が扱いやすくおすすめです。
各メーカーから専用のロッドが発売されていますが、XH以上の硬めのバスロッドや雷魚ロッド、H以上のショアジギングロッド、青物用のジギングロッドなどでも流用することができます。
メジャークラフト ソルパラ 岸タコ SPX-S702H/TACO
岸からのタコ釣りに特化して作られた専用モデルで、リーズナブルでタコ釣り入門にはもってこいのスピニングロッドです。タコエギやタコテンヤ用におすすめ。トップガイドを除く全てのガイドがダブルフット仕様で、高負荷がかかるタコ釣りでも安心して使える設計となっています。
メジャークラフト ソルパラ 岸タコ SPX-B702H/TACO
タコジグで足元を探っていくのに最適なベイトロッドです。スピニングモデルよりもパワーがあり、より大型のタコ狙いに適しています。もちろんタコエギやタコテンヤでのキャスト用としても使えます。ベイトタックルの扱いに慣れている方にはおすすめの1本です。
タコ釣りに使うリール・ライン

リール
タコ釣りに使用するリールはロッド同様ある程度強靭なものが必要になります。キャストをする場合は、初心者の方はスピニングリールがライントラブルも少なくおすすめです。番手は 4000~5000番で、ギアはノーマルでもハイギアでもどちらでも構いません。
ベイトリールの場合は船タコ用のものを選べば間違いありません。バス用のベイトリールでも使えますが、海水対応であること、PE3号以上を100m程度は巻けるラインキャパシティがあること、ドラグは5kg以上はあること、などが必要条件になります。
ダイワ レブロス LT4000-CH
7000円程度で買える手頃さが魅力のスピニングリールです。PE2号を170m巻けるラインキャパ、最大ドラグ12kgとタコ釣りでも十分使えるスペックとなっています。この価格帯にしては自重も255gと軽めで、一日キャストを繰り返すタコエギなどの釣りでも扱いやすくおすすめです。
プロマリン タコ専DX TSD4000
価格4000円程度のお手頃ベイトリール。PE8号50mが標準装備されており、そのままタコ釣りに使うことができます。ドラグ力は5kg。足元を探るタコジグを使った釣りにはぴったりな商品です。
ライン
ラインは伸びが少なく強度が強いPEラインを使います。太さはスピニングリールの場合は 2〜3号程度がメインで、長さは100mもあれば十分です。キャストせず足元を探るベイトリールの場合はもっと太い5号以上を50m程度巻ければ問題ありません。
PEラインは根ズレに弱いため、先端にフロロカーボンのショックリーダーを1mほど結んで使用します。太さはPEライン2〜3号ならリーダー8〜10号程度、PEライン5号ならリーダー20号程度が目安です。
尚、ベイトリールを使って足元に落とすだけであればリーダーは結ばずにPEライン直結でも問題ありません。
タコ釣りをする際の注意点
安全・快適にタコ釣りを楽しむためにも、いくつか注意しておきたい点があります。
漁業権に注意!

タコ釣りを楽しむ上で注意しなければならないのが、漁業権の存在です。漁業権が設定されている場所でタコ釣りを行うと 密漁となり、罰則を受けてしまいます。最悪その釣り場が釣り自体禁止になるという恐れもあるため、 漁業権のある釣り場でのタコ釣りは厳禁です。
漁業権が設定されているかは各自治体や漁協などのホームページで確認することができます。わからない場合は釣り場の漁協や最寄りの釣具屋などに問い合わせるようにしましょう。
危険種ヒョウモンダコに注意!

タコの仲間にはヒョウモンダコと呼ばれる種類がいます。10cmほどと小型ですが、フグ毒としても知られる 「テトロドトキシン」を持っている危険なタコです。食べるのはもちろん、釣り上げたヒョウモンダコに噛まれることでも中毒を引き起こし、死亡例もあります。
本来は日本国内では小笠原諸島や沖縄諸島などに生息する南方系のタコですが、近年海水温の上昇に伴い生息域を拡大させつつあり、本州でも各部で発見されています。
ヒョウモンダコは興奮状態になると青色の斑紋が体表に浮かぶ特徴があり、それにより他種と見分けることができます。もしもヒョウモンダコが釣れてしまった場合は素手では絶対に触らずに、魚バサミなどを使って速やかに逃がしましょう。
最低限のマナーを守ろう!

タコ釣りに限らず釣り全般に言えることですが、年々釣り人のマナーの悪さから釣りが禁止になっているポイントが増えてきています。特に多いのがゴミ問題と駐車問題です。
釣りによって出たゴミはその場にポイ捨てせずに必ず持ち帰って処分しましょう。また、 車も漁港内の指定された場所や漁港関係者の方の作業の邪魔にならない場所、もしくは近隣のパーキングに停めるなどして、迷惑にならないように心がけましょう。
他にも、立ち入り禁止の場所に入っての釣りや、夜間の騒音問題など様々なトラブルが考えられます。今後も末長く釣りを続けていくためにも、最低限のマナーを守って釣りを楽しみましょう。
タコ釣りを満喫しよう!

手軽なタックルで楽しめながら十分な引きも味わえる上に、釣って持ち帰ってから食べる楽しみも味わえるタコ釣りは近年徐々に人気を集めています。
釣ってよし食べてよしのタコは堤防で手軽に狙うことも可能で、船釣りでも楽しめる人気のターゲットといえるでしょう。ぜひこの機会にタコ釣りを始めてみてはいかがでしょうか!