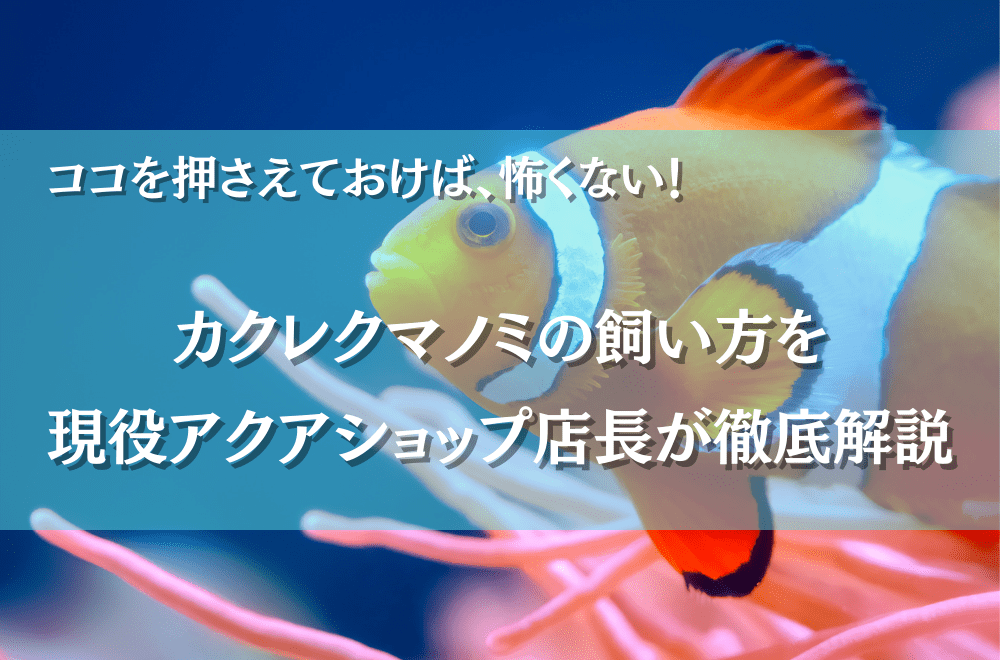
カクレクマノミの飼育法をプロが解説!初心者でもニモが飼える!
Share
カクレクマノミってどんな魚?
カクレクマノミは色鮮やかでかわいいので非常に人気が高く、熱帯魚の代表的な存在です。
メダカの餌を徹底解説!おすすめのメダカ餌や餌やりの量・頻度は?
見た目の特徴

カクレクマノミの全長は10センチ程で、オレンジの体に黒く縁どられたホワイトの帯は3本あり、非常に鮮やかで泳ぐ姿もとても可愛く特徴的です。
また、カクレクマノミは毒を持つイソギンチャクと共生しており、イソギンチャクを隠れ家とし、外敵から身を守ってもらっています。
カクレクマノミはなぜイソギンチャクと共生できる?

イソギンチャクが刺胞毒を出す条件は、海水に含まれているマグネシウム濃度より低くなった場合といわれています。
イソギンチャクは魚などの生物が触れた時に、魚の体表粘膜に含まれたマグネシウム濃度をイソギンチャクは感知して刺胞毒を出すかどうか判断していますが、カクレクマノミは他の魚と違って、体表粘膜に含まれているマグネシウム濃度が海水よりも濃いことから共生できるということがわかっています。
生息域と価格(相場)
カクレクマノミの価格は、ブリード物・ワイルド物・生産地によって違います。ブリード物は養殖が成功した頃はアメリカが生産地として日本にも輸入されていましたが、現在では日本でも養殖されているため、日本で流通しているブリード物は100%日本産です。
ワイルド物に付いてくる産地名としては、インドネシア、バリ、セブ、沖縄などです。1匹売りだと価格は1000~3000円±からですが、ペア売りとなると万越えもあります。
寿命

野生のカクレクマノミの寿命は、一般的には 10~20年といわれています。飼育下よりも自然界でのカクレクマノミの方が、自分に合った環境を求めて生きていくため、ストレスも少なく寿命は長くなります。
水槽内での飼育では 平均5~6年ぐらいと言われています。しかし、飼育環境や飼育方法によっては10年近く生きるカクレクマノミもおり、環境がよければ20年以上生きるようです。43年というギネス記録があります。
飼育難易度

飼育難易度については、ワイルド物の方が難易度は高くなります。ただし、ワイルド物でも最初の環境変化による病気になることもなく、又は病気を克服してしまえばブリード物と何ら変わりません。
一方で、ブリード物でも病気になってしまったり病気を克服できなければ、購入から1週間足らずで死んでしまうことも普通にあります。
/
カクレクマノミは性転換する繁殖生態をもつ

カクレクマノミは性転換を行う独特の生態を持っています。産まれた時は体の中に卵巣と精巣の両方を持っていて、オスでもメスでもありません。
基本的にはオスとして成長していき、数匹のグループ内で一番大きな個体がメスへと性転換します。そしてグループ内で2番目に大きなオスとカップルになり、繁殖を行います。その他の個体は繁殖に関わりません。
メスが死んだらそのオスがメスへと性転換します。一番大きな個体がメスになることで、より多くの卵を産むことができます。カクレクマノミは、一度ぺアになると相方が死んだりしない限り、何年もペアで居続け、繁殖を続けます。
/
スカーレットジェムを飼育しよう!餌選びのコツは?メスは入手困難?
カクレクマノミのバリエーション(改良品種)
カクレクマノミにも改良品種がいます。どのような品種がいるのか見ていきましょう。
ブラックオセラリス
突然変異で産まれた黒い個体を固定化したカクレクマノミの改良品種です。ただし、産まれた時から白と黒の色模様ではなく、最初は普通のカクレクマノミのような白とオレンジの体色をしています。
成長と共に黒くなってきて、黒色が色濃くなっていきます。
スノーフレークオセラリス
白いバンドの縁取りが不規則に乱れて、華やかな印象を受ける改良品種です。白いバンドの面積が大きく増えて、バンド同士ががつながって白面積がかなり多くなる個体もいます。
個体差も大きい改良品種なので、自分好みの個体を探す楽しみ方もあります。
プラチナオセラリス
体の大部分が白色で覆われている改良品種です。全身が真っ白な個体もいれば、ヒレだけにオレンジや黒の色が残る個体もいて様々です。
全身が白色で、一部のヒレだけ黒色になっている個体も見られることがあり、面白くもあり、可愛らしくも見えます。
スノーフレークブラックオセラリス
ブラックオセラリスのスノーフレークバージョンです。白いスノーフレーク柄に、ブラックオセラリスの黒い地色が映えて見える、とても美しい改良品種です。
こちらも個体差があるので、自分好みの個体を探す楽しみがあります。
ファンシーホワイトオセラリス
スノーフレークオセラリスとは違って、バンドの縁は乱れていないのでノーマル種と同じなのですが、バンドの入り方が乱れている改良品種です。
見た目は、一見ノーマル種に近いので、スノーフレークだと奇抜過ぎると感じる方には、こちらが可愛らしくスッキリ見えて良いかもしれません。
/
フロストバイトオセラリス
体の大部分を白色が覆うところはプラチナオセラリスに似ているのですが、ドット状(点状)に部分的に色が抜けた模様をしていることから、フロストバイト(凍傷)のような柄ということで、この名がつけられました。
目やエラの縁など、顔まわりも黒で縁取られたりもするので、そこもプラチナオセラリスとは趣が違って見えます。
ミッドナイトオセラリス
ブラックオセラリスから白色を排除する方向に改良された品種で、全身が黒色のカクレクマノミです。なかには部分的にオレンジ色や白色が残っている個体も見られることがあります。
とはいっても、改良が進むにつれて黒一色の固定率が上がって、今ではまるで別種の魚に見えるくらいです。
ネイキッドオセラリス
ノーマルのカクレクマノミから白バンドを排除し、オレンジ色の一色だけにした改良品種です。イレギュラーバンド個体で、これに似た個体を見かけることはあります。
ここまでオレンジ一色だと、これまた別種に見えるくらい違いがあり、色合いから可愛らしく見える改良品種です。
/
カクレクマノミの飼育方法
カクレクマノミはお店に来てから一度安定してしまえば、とても丈夫で飼いやすい海水魚です。カクレクマノミをこれから飼育する上で知っておきたい基本情報を解説していきます。
水槽・フィルター
水槽サイズは、小さくても45㎝規格水槽くらいからがおすすめです。30㎝水槽にカクレクマノミ1匹くらいの飼育も可能ではありますが難しいので、水槽はなるべく大きな方が水質悪化もしにくく好ましいです。
30㎝サイズの水槽であれば、30キューブ(30×30×30)水槽の方がまだ良いですし、できるなら60cm規格水槽がおすすめです。
フィルターは、小型水槽であれば外掛け式フィルターが手軽で濾過能力的にもおすすめですが、海水魚用の外掛け式フィルターとしてプロテインスキマーが付いた外掛け式フィルターがあり、特におすすめです。
45㎝水槽からであれば外掛け式フィルターはもちろん、上部式フィルターや外部式フィルターも選択肢として挙げられます。
飼育匹数については、飼育者がどれくらいの頻度で水換えをできるのかによっても違ってきます。また、カクレクマノミは複数飼育していてもイジメや喧嘩が起こりやすい魚種であることや、いずれペアができてしまうと他のカクレクマノミはその水槽では弱い立場になって混泳できなくなってることもあります。
そのため、基本2匹飼育が無難だと考えておきましょう。大事なのは水槽の水量なので、可能な限り小さな水槽は選ばないようにしましょう。
水温・水質
水温は20~30℃が飼育できる水温ですが、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育も兼ねるなら、水温は28℃を上限として、夏はそれ以上水温が高くならないようにしましょう。20~28℃と覚えておくのが良いでしょう。
保温はヒーターで温めるのはもちろんですが、夏場に水温を下げる方法としては扇風機や水槽用クーラーがあります。もちろん、部屋をクーラーで冷やすことができれば1番良いですが、それができない場合は扇風機や水槽用クーラーが必要です。扇風機であれば、水槽用扇風機が水槽に取り付けることができるので便利です。
ただし、扇風機で下げることができる水温は2~4℃程度なので、これでも適水温にできないのであれば、水槽用クーラーか部屋ごとクーラーで冷やすなど必要になります。水質については、よほど長期間水換えを怠らない限り、水換えさえしていれば気にしなくても大丈夫です。こればっかりはテスターで水質を計ってみないことには何とも言えません。
例えば100ℓ水槽にカクレクマノミが1~2ペアであれば、1年に1回程度の水換えでも飼えてしまいますが、水槽内は富栄養化によるコケや海毛虫などの発生で見栄えは悪くなりがちです。
照明(ライト)
照明は生物には欠かせないものです。水槽用ライトとして現在はLEDライトが主流ですが、サンゴやイソギンチャクなどの無脊椎動物は強い光を必要とするものが多いので、基本的には明るいライトが良いと言えます。
ただし、そればかりではなく、逆に強い光を苦手とする種類もいるので、強い光が必要な無脊椎動物には強いスポットライトをあてて、全体的にはほどほどの明るさのライトをあてる、というようにする方法もあります。
カクレクマノミに至っては、ライトの強さはこだわらなくても大丈夫です。LEDライトにも明るさの違いの他、色合いの違いもあるので、そのような観点からライトを選ぶ方法もあります。
例えば、白色のライトだけのものもあれば、赤や青も発色するライトもあるので、お好みで選んで大丈夫です。ライトの照射時間は8~12時間にしましょう。タイマーを使用して照射時間をコントロールするのがおすすめです。
ライトが明るいほど、照射時間が長いほどコケが発生しやすくなるとも言えますが、コケ発生の要因は飼育水の富栄養化など他にもあるので、コケ取り生物も飼育するほかに、コケを抑制する商品も上手く使って水槽の美観を保つようにすると良いでしょう。
/
カクレクマノミの餌

カクレクマノミの餌としては、ドライフードや冷凍飼料があります。ドライフードは顆粒タイプやフレークタイプが一般的ですが、餌の形状だけでなく栄養的にも違いがあって、動物質タイプや植物質タイプ、病気に対する抵抗力を上げることができるタイプなど、各社で特徴があります。
フレークタイプの餌は水槽内を汚しやすいと思われがちですが、これは見た目的なことからくる勘違いであって間違いです。結局のところ、残り餌がどれだけあるか、栄養価がどれだけあるかで、水の汚れやすさが違ってきます。
蛋白質が豊富な栄養価の高い餌ほど水を汚しやすいのです。顆粒の餌の方がフレークの餌より栄養をより摂りやすい、という話がありますが、これは言い換えれば顆粒の餌の方が水を汚しやすい、とも言え、実際もフレークの餌の方が水は汚れないように感じます。
海水魚に使用される冷凍餌は、ホワイトシュリンプやブラインシュリンプのアダルト(成体)が使用されます。自然の餌なので良い餌です。栄養価も消化吸収も優れています。
冷凍飼料に対してドライフードが劣る点は、消化吸収の点です。数字上は栄養価に優れたドライフードでも、それがちゃんと消化吸収されて活かされるかといったら、実際は少し違うというわけです。
/
カクレクマノミ飼育にイソギンチャクは必要?

結論から言うと、カクレクマノミの飼育にイソギンチャクは必要ありません。しかも、イソギンチャクも一緒に飼育する場合、むしろイソギンチャクの方に気を配った飼育環境にしなければなりません。カクレクマノミよりイソギンチャクやサンゴなど無脊椎動物の方が飼育が難しいからです。
水流の強さや方向、照明の強さ、水質、イソギンチャクが移動した場合の水中ポンプへの巻き込み防止策が必要など、気をつかうべき点が色々とあるのです。もちろん、イソギンチャクにも飼育の簡単な種類から、難しい種類までいるのですが、カクレクマノミが隠れやすいイソギンチャクの種類は決まっています。
ただし、隠れるとは言われていない種類のイソギンチャクにカクレクマノミが隠れることもあるので、一概には言えないところもあります。更に言うと、カクレクマノミの繁殖にすらイソギンチャクは必要ありません。
私のお店でもイソギンチャク無しで、しかもワイルド物のカクレクマノミが何回も産卵・繁殖していて、15年以上生きています。ここまで踏まえたうえで言い方を変えると、イソギンチャクを上手く飼育できる環境であれば、カクレクマノミも飼育できてしまうということです。
/
カクレクマノミの混泳

まず、どの魚種だろうが共通して言えることとして、混泳に絶対は無い、ということは覚えておいてください。カクレクマノミは他の魚と混泳できる魚ですが、混泳が上手くいかない可能性が高い魚種としては、同じカクレクマノミや、クマノミの仲間などが挙げられます。
カクレクマノミ同士でも喧嘩やイジメが起こりやすいですし、ペアができてしまうとペアはその他のカクレクマノミに対して排他的な行動をとるようになります。自然界のように広さがあれば混泳が成立しやすいので、水槽がなるべく大きい方が良いということになります。

具体的には90㎝以上の水槽であれば何とかなったりしますが、60㎝水槽では上手くいかないパターンが多いです。あとは同じスズメダイの仲間も基本的には気が強いので、混泳が上手くいかないパターンもあります。
その他の魚であれば混泳させやすいと考えていいのですが、何事も試してみなければわからないので、飼育者自身の経験を積むとして実際にやってみてください。同じ混泳の組み合わせでも、成功することもあれば失敗することもあるのが理解できると思います。
飼育環境や魚の大きさや密度などで、混泳の可不可は違ってくるものです。
/
カクレクマノミの病気と治療法
カクレクマノミがかかりやすい病気としてトリコディナ症があります。海水魚の代表的な病気として、白点病もありますが、治療法としては共通している部分も多いので、今回はトリコディナ症に焦点を当てて解説していきます。
トリコディナ症
原因
原生動物による病気で、繊毛虫類のTrichodina属の寄生により起こります。水を介する間接接触によって魚体に取りついた繊毛虫は運動によって水中を遊泳したり、魚体上を動き回ったりします。
病原体の主な食物は上皮細胞崩壊物や、それらを栄養源として増殖する細菌などであって、直接魚体から栄養をとったりすることはありません。
症状
カクレクマノミが体を擦り付ける行動が見られたりもします。カクレクマノミのヒレに白い濁りが入ったり、ヒレが閉じ気味になったり、体表粘膜に白く膜がかかったように見えたりもします。
泳ぎ方も普通とは違うように見えたりもします。
予防
他の病気や水中の有毒物質によってトリコディナ症が引き起こされやすくなりますし、何らかの原因によって魚体にできたスレなどの傷はトリコディナにとっての食物の増殖が促進されることにつながるので、このようなトリコディナの増殖要因を作らないことが肝心です。
水溶性フコダインも有効という報告があります。
治療
2分程度淡水浴をします。その間、指で魚体をなでるようにして体表面の粘膜と共に病原体を取り除きます。
2分淡水浴のあとは半分海水を足し、また2分後に半分水を捨てて半分海水を足し、また2分後・・・と繰り返し、比重が水槽とほぼ同じになったらカクレクマノミを水槽に放します。
これを治るまで毎日続けます。なお、白点病も同じ治療でかまいません。
/
初心者がカクレクマノミ飼育を始める際に気をつけるべき3つのポイント
カクレクマノミ飼育を始める際に気をつけるポイントまとめてみました。
とにかく状態が1番の重要ポイント
1番の重要ポイントは、当たり前ですがカクレクマノミの状態です。元気で痩せていないことを確認しましょう。
餌をねだってくる様子が見られれば万全ですが、人影に驚いて水槽の奥に引っ込んでしまうことなども日常的にあることなので、判断を正確にできるようにしてください。
なおかつ、お店に届いてから2週間以上経過していれば全く心配はいりません。もし逆に、お店にいることでいつも状態が悪くなっていくようであれば、そのようなお店からは入荷日に購入してしまうのも方法の1つです。
飼育水槽はなるべく小さくない方が良い
飼育水槽はなるべく大きめが良いです。45㎝規格~60㎝規格水槽が取り扱いもしやすく、おすすめです。それより小さい水槽であれば30㎝キューブ水槽が良いです。
それ以下の小さな水槽でも飼育は可能ですが、水質の維持管理が難しくなるので、あまりおすすめはしません。小さい水槽で飼う場合は、濾過環境が既にできていないと簡単に魚が死んでしまいます。
水槽が大きければ大きいほど、魚を飼育しながら濾過環境を立ち上げることが可能になるので、余裕があるということになります。
最初はブリード物がおすすめ
1番最初に飼うカクレクマノミなら、ブリード物をおすすめします。ブリード物であれば、人間による飼育環境下に慣れているため、飼いやすいということになるからです。
大自然の海原にいるカクレクマノミと違って、人間の管理下による水槽環境への慣れや、人工的な餌への慣れなど、ワイルド物と最初からハードルの高さが違います。もし、ブリード物とワイルド物を混泳させる際は、いつも以上に病気に気を配るのもポイントです。
/
カクレクマノミを飼育してみよう!

「海水魚飼育って難しいんでしょ?」ってイメージがあるかたも少なくないかもしれませんが、私がいつも海水魚飼育をスタートするかたにおすすめするのが、カクレクマノミです。それだけ飼いやすいということです。
「いつかはカクレクマノミ」ではなく、海水魚飼育デビューからおすすめできるのが、カクレクマノミなんです。この記事を海水魚デビューのきっかけにして、マリンアクアリウムを楽しんでください。
タライロンの飼育法や最大サイズは?獰猛な肉食魚を飼う上での注意点とは


















