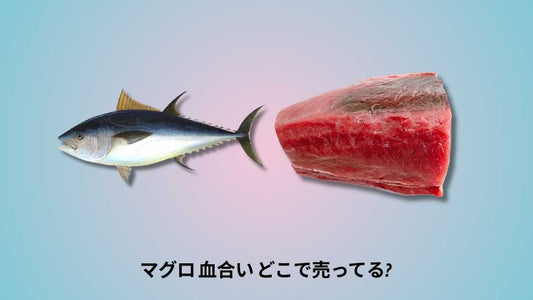ドクターフィッシュの角質除去効果と飼育方法!値段も安くて丈夫な熱帯魚!
Share
ドクターフィッシュ(ガラ・ルファ)とは

ドクターフィッシュはコイ目コイ科ガラ属に含まれる ガラ・ルファ(学名:Garra rufa)という魚の通称で、人の手足の角質を食べてくれることからこのように呼ばれています。トルコやイラクなどの西アジアの河川に広く分布しており、37度程度の高水温にも耐えられる特徴を持っています。かの有名なクレオパトラもドクターフィッシュを愛用していたとも言われています。
全長は最大でも10cm程度と小型で、普段は石などに付着している藻類などを食べています。ドクターフィッシュは、水槽のコケ取り生体として有名なサイアミーズフライングフォックスに近縁な魚です。
ドクターフィッシュの寿命は7年程度と言われており、生後2年ほどで成魚になります。ストレスなどには強く、とても育てやすいため観賞魚としても流通しています。
/
ドクターフィッシュによる3つの効果
ドクターフィッシュにはどのような効果があるのか、具体的にご紹介していきます。
ピーリング効果

ドクターフィッシュは手足の古い角質を食べてくれることから、肌を活性化させ、肌トラブルを改善してくれるピーリング効果があります。人間の肌は一定周期で剥がれ落ちて新しい肌に生まれ変わりますが、この周期が遅れるとニキビや乾燥、シミなどのトラブルの原因になります。
ドクターフィッシュは、古い角質を取り除いてくれることで、肌改善に効果が期待できます。
マッサージ効果

ドクターフィッシュが肌をついばむと適度な振動や刺激により、皮膚の代謝をあげてくれると言われています。自然のマッサージのような効果を産んでくれるのも、ドクターフィッシュの特徴です。
リラクゼーション効果

適度な刺激によるマッサージは日常的に疲れている現代人にとって、リラクゼーション効果もあると言われています。機械や人の施術などとは少し違った刺激をドクターフィッシュは与えてくれ、十分に心も体もリラックスすることができます。
/
ドクターフィッシュに隠された危険性
様々な有益な効果があるとされるドクターフィッシュですが、一方で危険性も指摘されています。
感染症の可能性も
危険と言われる理由の一つ目は、感染症についてです。
ドクターフィッシュ自体は口歯はありませんが、肌に傷口などがあってその人がなんらかの感染症を持っていた場合、その部分をついばんだドクターフィッシュが別の人の角質を食べることで他人に感染させてしまう可能性もあると言われています。
このことから、 一部の商業施設や海外の一部の国や地域では、ドクターフィッシュの使用が禁止されている場所もあります。
ガラ・ルファ以外のドクターフィッシュ
ドクターフィッシュといえばガラ・ルファが一般的ですが、その他にも同様の働きをしてくれる魚がいます。
海外ではタウナギやカンディル、カワスズメ科の一種などをドクターフィッシュの代わりに用いた例もあるようですが、これからの魚は鋭い歯を持っていたりと、安全性が保証されていません。もしも、海外などでドクターフィッシュのサービスを見かけたら魚種にも注意しましょう。
/
ドクターフィッシュは大きくなると角質を食べない
実はドクターフィッシュが人の角質を食べるのは 生後半年から2年半くらいまでの幼魚〜若魚期のみとされています。また、ドクターフィッシュは好んで角質を食べているわけではなく、他のエサがない空腹時などに仕方なく食べるようです。
そのため、飼育する際はできるだけ熱帯魚用の配合飼料を与えてあげるようにしましょう。
また、ドクターフィッシュが集まりやすい人・集まりにくい人というのがいると巷では言われることがありますが、これはたまたま近くにいる方に集まっているなどの場合がほとんどで、手足の汚れの程度(角質の多い少ない)で差が出るという訳ではないと思われます。
/
ドクターフィッシュは入手も容易で、値段も安い
ドクターフィッシュの代表であるガラ・ルファは比較的流通量も多いため入手も容易です。値段は 1匹200~400円程度と安価です。魚自体の値段は安いですが、飼育する際はしっかりとした設備を用意しましょう。
特に、ガラ・ルファは暖かい水を好むのでヒーターが必須です。
ドクターフィッシュの飼育方法
ガラ・ルファは高水温を好む点に気を付ければ、比較的簡単に飼育が可能です。ここでは、ガラ・ルファの飼育方法などをご紹介します。
水槽サイズ・フィルター
ガラ・ルファは小型魚なので、30cmクラスの水槽から飼育可能です。しかし、鑑賞目的だけでなくドクターフィッシュとしても楽しみたい場合は、ある程度の個体数が必要なので大きい水槽が必要です。
ここで、注意していただきたい点があります。前述の通り、本種は成魚になると角質を食べなくなることに加え、 成長するにつれ縄張り意識が強くなり、同種に対しては攻撃的になる傾向にあることです。
そのため、ガラ・ルファが大きくなってから飼育環境が崩壊しないよう、複数飼育したい時は個体数に応じた大きな水槽を用意しておいてください。
フィルターについては、本種はそれほど水を汚しやすい魚種ではないため、お好きな種類で問題ありません。価格やメンテナンス性を考慮すると、外掛け式や上部式が使いやすいのでおすすめです。
水温・水質
ガラ・ルファを飼育可能な水温は 約23~37度です。ただし、低温側では活性が低くなりあまり動かなくなってしまうため、観賞魚として日常のコミュニケーションを楽しみたいのであれば、年間を通して30~35度程度の高めの水温をキープした方が良いでしょう。
このことから、日本の大部分の地域においては夏場以外はヒーターが必須です。必ず、水槽サイズに適応したものを用意してください。
水質については 中性~弱酸性を好みます。水質への適応力が高いため、基本的には中性付近を保てれば問題なく飼育可能ですが、弱酸性の水質で飼育することでより元気になる個体も居ます。水質を弱酸性にしたい時は、底床にソイルを使用したり、流木やマジックリーフを入れると良いでしょう。
/
エサ
ガラ・ルファの食性は雑食性で、自然下では藻類の他に水生昆虫、魚の死骸など、植物質の物も動物質の物もよく口にしています。また、本種の遊泳層は主に下層です。
これらのことから、餌はプレコ用やコリドラス用に作られた、沈下性の人工飼料が適しています。それらをメインに、たまに冷凍アカムシなどの生餌を与えると、栄養バランス的にも本種にとって理想的な食環境となります。
与え方としては、 1日に1回または2回に分けて、1回あたり3~5分ほどで食べきれるだけの分量を与えてください。本種は口が小さいので、人工飼料を食べにくそうにしている時は、小さく砕いてから与えると良いでしょう。
食べ残しをそのままにしておくと水質の悪化が早くなるため、食べ残した時は速やかに飼育水中から取り除いてください。
レイアウト
ガラ・ルファは単独飼育であればレイアウトの自由度は高いです。本種は下層で生活することもあり、底床は入れたほうが良いです。底床の種類は、水質をアルカリ性側に傾けるサンゴ砂のような物以外が推奨され、前述したように、弱酸性の水質を好む傾向にあるためソイルとの相性も良好です。
ソイルの使用に問題がないこともあり水草との相性も良く、それに加えて石組みや流木などを組み合わせて自由に水景を作成しても構いません。特に、流木は水質を酸性に傾ける機能も持つので、やはり相性は良好です。そして、本種はある程度の水流がある環境を好むため、必要に応じてディフューザーなどを導入すると良いでしょう。
複数飼育する時は喧嘩にならないよう、隠れ家になるシェルターや水草を多めに入れてあげる必要があります。
/
コケ取りとしてドクターフィッシュは有効?
ガラ・ルファは自然下では藻類をよく口にしているため、水槽内に発生したコケも食べます。それだけでなく、雑食性なのでタンクメイトが食べ残した餌も食べてくれます。さらに、他種に対しては無関心であることが多く混泳相性も良いことから、コケ対策を含むクリーナー生体として優秀です。
ただし、ガラ・ルファが好む水温は多くの熱帯魚にとって高温すぎるため、クリーナー生体として活躍できる場面は限られてきます。
クリーナー生体として導入する場合でも、ガラ・ルファ用の餌は必ず用意してあげてください。というのは、本種はコイの仲間だけあって小型魚の割には餌の要求量が多く、水槽に自然発生するコケやタンクメイトの食べ残しだけでは、栄養が不足する恐れがあるからです。
特に、本種の特徴として植物質の物を多く要求することが挙げられるため、プレコ用の配合飼料など植物食性が強い魚種のために作られた配合飼料は用意しておいてください。
また、残餌が出るような給餌方法は水質維持の観点から推奨できないので、タンクメイトおよびガラ・ルファそれぞれに、食べ残しが出ないだけの量の餌を与えるようにしましょう。
/
ドクターフィッシュの繁殖方法
ガラ・ルファは水槽内で繁殖が可能です。ここではガラ・ルファの繁殖方法についてまとめてみました。
雌雄の見分け・繁殖環境
ガラ・ルファは、オスとメスで見た目の違いがほとんど現れないため、外見での見分けは非常に難しいと言えます。
そのため、繁殖を狙う場合は、大きめの水槽にある程度の個体数を入れて、自然にペアリングが成立することを期待することになります。
水槽内の環境としては、通常どおりに飼育していてしても繁殖するケースもありますが、なかなか繁殖に至らない場合は、 多めの換水を行って水温を25~29度ほどに下げてみてください。
これは、本種の野生個体は現地の雨季に繁殖活動を行っており、水質や水温の変化が繁殖のトリガーになり得るからです。
産卵・ふ化
十分に成熟した健康なオスとメスが同一水槽内に居れば、普通に飼育していてもペアが形成されて産卵にまで至ります。本種はバラマキ型の産卵形態を持つので、産卵床としてウィローモスといった、背が低く密度のある水草を入れておいてください。
本種は卵を見つけると食べてしまうため、卵を隠す必要があるからです。確実に繁殖させたい場合は、卵を確認したら採卵して親魚から隔離すると良いでしょう。
卵は25度程度の水温でも数日でふ化して稚魚が誕生します。隔離した卵から生まれた場合は、そのまま稚魚の育成に入れますが、親魚と一緒の水槽だと食べられる危険があるので、採卵しなかった場合は隔離してください。
稚魚の育成
稚魚水槽の水温・水質は親魚と同様で問題ありません。しかし、稚魚は小さいためフィルターに吸い込まれてしまわないよう、取水口にスポンジを取り付けるなどの措置をしてください。また、強い水流が発生していると衰弱死する恐れがあるので、エアレーションなどの配置にも注意が必要です。
産まれたばかりの稚魚は腹部に卵黄嚢を持ち、そこから栄養分を吸収して成長するため、餌を与える必要はありません。餌を与えたところで食べてくれないため残餌となり、水を汚すだけなので静かに見守りましょう。餌が必要になるのは、養分を吸収し終えて卵黄嚢が消失したころです。
この頃になると泳ぎだすまでに成長しているため、ふ化させたブラインシュリンプや、親魚用の人工飼料をすり鉢などで細かくした物を与えると良いでしょう。ちなみに、ブラインシュリンプやアカムシといった、動物質の物を多めに与えた方が成長が速くなり、死亡率が高い時期を早期に脱することが可能です。
/
ドクターフィッシュがかかりやすい病気
ガラ・ルファは丈夫な魚種なので、かかりやすい病気は特にありません。というよりは、ガラ・ルファが好む高水温下では、一般的な熱帯魚の病気の原因となる寄生虫や細菌は、ほとんど活動できなくなるのです。よって、ガラ・ルファが好む35度くらいの水温で飼育する場合は、病気の心配はほぼないと言えます。
しかし、他の魚種と混泳させるために、30度未満の水温で飼育する場合はその限りではありません。ガラ・ルファにとっての低水温下では活性が低くなり、それに伴って免疫力も低下する恐れがあるので、運動性エロモナス症といった他の熱帯魚と同様の病気に注意が必要です。
また、本種は水面から飛び出しやすいため、しっかりと固定できるフタは必ず用意しておいてください。そして、フタを取り付ける時、隙間はしっかりとふさいでおきましょう。本種は小型であるため、意外に思える小さな隙間からでも脱出する例があります。
/
ドクターフィッシュはとっても働き者!

人の角質を食べる働き者のドクターフィッシュは、その独特の生態などからとても魅力がある熱帯魚です。また、寸詰まりな体型と口に生えた短いひげはとっても可愛くて癒されます。
水槽の掃除をするときにドクターフィッシュにもふもふされるなんてのも飼い主ならではの楽しみかもしれません。気になった方はぜひ、飼育にチャレンジしてみてくださいね。
大磯砂は安価で扱いやすい定番の底床材!フィルターや水草との相性は?